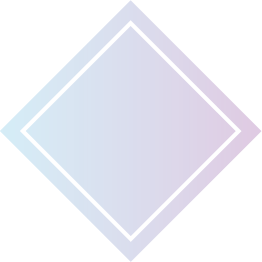神が、ゾンビ映画にハマった。
あるいは、ゾンビゲームかも。
だからこの世界をゾンビだらけにしようとしている。現実にゾンビを持ち込もうとしている。
未知の病原菌だとか、遺伝子の突然変異だとか、秘密裡に行われていた実験兵器の失敗だとか、二人はそういった仮説を立てているようだが、違う。
現実はもっと非科学的で、いたってシンプルだ。
そんなことを考えている俺の前で、頭の良い会話が続く。先程知り合ったばかりの大学生が、特殊部隊の軍人女と議論を戦わせている。
その近くでは、可愛い顔つきの華奢な女が不安げな顔で二人のやりとりを見守っている。
彼らから少し離れたところでは、明らかに気弱そうなサラリーマンのオッサンが、怯えた目で絶えず部屋の入り口に目をやっている。
バリケードを張ったビルの一室にいるのは、俺を入れて五人。
辛くもゾンビから逃れてきた生存者だ。
俺はそれぞれの顔を見比べる。
大学生の男は、かなりのイケメンだ。会話の内容から察するに頭も良い。つい一時間前、ゾンビに襲われかけていた謎の美女を軍人女との見事なタッグで救い出した。
イケメン、頭脳明晰、そして強い。
こいつは、生き残るだろう。俺には分かる。
大学生と議論を戦わせている軍人女は、合衆国から派遣されてきた特殊部隊の一員で、浅黒い顔のアメリカ人だ。流暢に日本語を操っているのは、昔日本にいたことがあるからだとか何とか言っていたが、そこはお約束だ。
ゾンビが発生した原因はだいたいアメリカ政府にあると決まっているので、その秘密を知る者としてこの女はここにいる。
大学生の男と協力して謎の美女を助け出したとき、火炎瓶を使ったかなりトリッキーなやり方でゾンビたちを撃破したが、細かいことは省略する。
説明しなくとも、だいたい同じようなことを、星の数ほどあるゾンビ映画がやっている。
軍人女は、屋上のヘリポートへ俺たちを導く。
しかし、こいつも道半ばで死ぬ。
俺には分かる……いや、もしかしたらゾンビに噛みつかれた後も理性を保ち、徐々にゾンビ化しながら脱出地点まで俺たちを連れていった後で完全なゾンビになり、襲いかかってくるかもしれない。
どちらにしても、死ぬことは決まっている。
そして、彼らが助けた謎の美女。スパイ紛いのアバズレではなく、可愛いタイプの謎の美女だ。アメリカで不思議な実験をさせられていて、何かの適合者であるらしい。
彼女自身よく分からないと言っていたが、俺には分かる。
彼女は血液から対ゾンビ用のワクチンを作りだせる。
俺は謎の美女を見ながら、一発やらせてくれないかなと思うが、役者が違うので不可能だ。やるとしたらこの大学生しかいない。確実にこいつらはやる。
だが、それはもう少し先の話だ。
この女は、もちろん生き残る。この女が生き残って、人類を救うワクチンが出来上がる。
そして、こいつらはやる。俺には分かる。
「こ、こここの部屋、だ、大丈夫でしょうか……? か、かかか感染者たちが、バリケードを突き破ってきたら……!」
サラリーマンのオッサンが、耐えきれず軍人女に聞く。オッサンの顔は常に恐怖が張り付いていて、膝がガクガクと震えている。出会い始めからずっとこんな調子で、謎の美女以上におろおろと状況を傍観しているばかりだ。
こいつは、もうすぐ裏切る。俺には分かる。
恐怖に耐えかねて部屋から飛び出したところをゾンビに襲われる。それだけならまだしも、オッサンの開けたドアからゾンビがわらわらと押し寄せ、俺たちは窮地に陥る。
余計なことをして、このオッサンは死ぬ。
個人的に、ゾンビより先にオッサンの方を殺しておくべきだと思うが、もちろん口には出さない。全てはなるようになるからだ。
そして俺についてだが、もちろん死ぬ。
死なないはずがない。
俺は脱出寸前のところで、大学生を足蹴にして我先にとヘリに飛び乗ろうとする。今まで協力してきた仲間を華麗に裏切る。オッサンの裏切りが自身の弱さから出た不可抗力的なものに対して、俺の裏切りは意図的だ。自分だけ助かろうとする。だから、死ぬ。
仲間の中で最も無残な死に方をするだろう。俺には分かる。
なぜならば俺は、職を転々としているフリーターで、ギャンブルで作った借金もあるし、人から借りたまま返していない金も山ほどある。都合良く使い捨ててきた女はたくさんいるし、手グセが悪くて物をよく盗む。日頃から金の絡む悪巧みばかりしている。言うまでもなく人相も悪い。悪人ヅラだ。
というか、程度の低い悪事を働く小悪党だ。
いや、小悪党でもなくなった。
つい先程、人殺しをやってのけた。
ゾンビから逃げようとする人間を押しのけ、我先に高所に続くハシゴを登り、後からやってきた人間をゾンビの群へ突き落として時間を稼いだ。
その中には警察官もいた。どさくさに紛れて俺は銃を奪った。
今もジーンズのポケットには銃がしまってある。いざという時に、これで仲間たちを脅す。そのための銃だ。
「彼らから逃れるには、どうすればいい?」大学生が聞く。
「ビルの屋上で仲間が待ってる。ヘリで脱出するわ」軍人女が言う。
ほら出た、ヘリだ。
「廊下にいる感染者たちはどうする?」
「彼らは光に弱いの。強力なライトを用いて……」
「感染者がやってきたところへ……」
二人は真剣な顔で作戦を立てている。気弱なオッサンのせいで、全ておじゃんになる虚しい作戦だ。
俺は再び謎の美女を爪先から頭のてっぺんまで舐めるように眺めまわして頼むから一発やらせてくれないかなと思う。もちろん夢のまた夢であることは分かっているので、せめて視姦しておく。
それにしても、彼らはゾンビのことを「感染者」だとか「彼ら」だとか「実験体」だとか言う。「ゾンビ」なんて言葉はおくびにも出さない。
わざとらしいくらい「ゾンビ」を避けて通るのは、彼らが「ゾンビ」を知らないからだ。
ゾンビは世界の外側にいる見物人が定義付けするものであって、病原菌に侵されて出来たゾンビは「感染者」、実験の失敗で出来たゾンビは「実験体」、その他偶発的にゾンビらしくなってしまったものに対しては、人間ではないにしてもどう定義していいものか分からないという意味を込めて「彼ら」と呼ぶ。
他にもさまざまな呼称はあるだろうが、「ゾンビ」だけ、その限りではない。
だからそれ、ゾンビだろ。
というのは、メタ的に状況を認知している者だけに与えられた呼び名だ。
俺も、彼らがゾンビのことを「感染者」と呼ぶたびに「だからそれ、ゾンビだろ」と思うが口には出さない。俺は空気を読む男だ。
いつのまにかオッサンが消えていた。扉が少しだけ開いているから、隙を見て逃げ出したんだろう。ゾンビがこの部屋に押し寄せてくるのは時間の問題だ。
大学生も軍人女も、狭い密室で人が一人いなくなっていることに、何故か気づかない。謎の美女は絶えず大学生の顔に目をやっているので、先ほどの救出劇も相まって彼に惚れ始めている。
しかし、大学生は彼女の想いに気づかない。こいつには年相応の性欲が備わっていないんじゃないかと思うほど、精悍な顔は謎の美女を見向きもしない。ひたすらに全員が無事に生還するための最善策を練っている。
残念ながら、生き残るのは二人だけだ。軍人女は陽気な黒人ではない。だから生き残りの三人目にはなれない。
イケメンと美女を除いて、俺たちは全員死ぬ。
しかし俺は、ゾンビになることを恐れてはいない。
ゾンビになれば、苦しい借金や、叶わない性欲や、悪いことばかりを考えるさもしい心からおさらばできるからだ。
俺はゾンビになることを死ぬこととして捉えているが、もしかしたら、ゾンビになっても意識が残っているかもしれない。ただ、ゾンビの本能というか、「うー」とか「あー」とか言いながらその辺をうろつき回り、生きた人間がいたら飛びついて仲間にする習性が加わるだけで、俺は文字通り意識的に、ゾンビ化した後の生活を満喫できるかもしれない。
いや、俺がゾンビを良しとしているのは、そんな一縷の望みにすがっているからではない。
ゾンビになって、俺の意識や生命がなくなってしまったとしても、それはそれで構わない。
俺は、ゾンビを恐れていない。人間をやめることを恐れていない。もっと言えば、人間だろうがゾンビだろうがどうでもいい。
最近、全てがどうでも良くなってきている。
俺は懸命に脱出劇をくわだてて、そしてその通りに予定が調和していく彼らを、可哀想に思う。
人間であることを正とし、ゾンビになることを悪とする。
そしてその先を考えないイケメンと美女を可哀想に思う。
ドアを突き破って大量のゾンビが押し寄せてきた。
俺たちは慌てて窓ガラスを割り、外に出る。
外壁に設置されたハシゴを登る最中、俺は目下を見下ろした。
窓から身を乗り出したゾンビたちの群れの中にあのオッサンの姿も見える。
心なしか「あー」とか「うー」とか唸り声を上げている土気色の顔が、幸せそうに見えた。