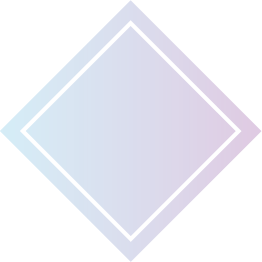暇なときに考えるのは、ソファと風船のことばかり。
横になって目を閉じ、空想をめぐらす。ソファと風船。
初めはソファ。大きなサイズ。頭の先から爪先まですっぽりおさまるほど大きい。
材質は硬くもなく柔らかくもない。叩くとペチペチと音がする泥水に似た弾力性。横になると沈むけど、底なし沼にならない程度。カーラーのついた前髪っぽい肘掛けが左右に二つある。
ここからが肝心、色を選定する。
一番重要、かつ一番楽しい部分だ。
想像するたびソファの色は変わる。先週はピンク色のギンガムチェック。先々週はサーモンピンク。水色の細かな魚のシルエットがついていた。あたしは爽やかな色が好き。
しかし、今はナイーブな気分なのでスモーキーピンクにする。大人の女性の唇みたいな色。雰囲気を台無しにしないよう、適度な大きさ、適度な量の星印をあちこちにまぶす。
大人っぽいカラーリングと子供っぽいシルエットが合わさって、抜群に可愛くてスパイシーなソファになる。
そのソファは大きな部屋に、ぽつんと一つ置いてある。
いつか見た美術館の作品貯蔵庫。思い出の中の広く無機質な空間に。
そこで、風船の出番だ。
今回の風船はデザインをひねらない。スモーキーピンクと同じ彩度のネイビーブルーに統一する。ミリタリー風の攻撃的な色だ。その風船にもソファと同じ、黒い星を散りばめる。
あたしは首を動かして、ぐいと風船を引き寄せる。ソファの方へ持ってきて、細いロープでソファと風船を繋ぎ合わせる。ロープはワイヤー製なので簡単には切れない。
念の為、風船にガスを補給する。
このガスも特殊な化学薬品で出来ていて、一度注入したら二度と萎まない。
ぱんぱんに膨らんだ風船は割れない。なぜならば、風船に使われているゴムも特殊な化学製品で出来ている。
二十一世紀において、科学は偉大な進歩を遂げた。あたしの風船は萎まないし、破裂しない。
指先に力を込めて念じる。
浮け。
足下が傾く。斜め上に。続いて頭の方も浮く。
あたしが沈んだ泥沼のソファが、風船によってふわりと浮き上がる。心地よい風に揺れるハンモックのように左右に揺れながら、ゆっくりと地上を離れてゆく。
美術館の天井にはぶつからない。
ソファが保管された倉庫に屋根はない。遠い昔、トタン屋根が何者かによって外された。
その何者かは、もちろんあたし。
こうして空へ飛び立ったソファは、ゴミだらけの不穏な街を目下にしながら南を目指す。
太陽は燦々と輝き、あたしの旅路を見守る。
飼い猫が飛び乗ってくる。連れて行く気はなかったけれど、名残惜しそうにこちらを見るので仕方なく拾ってあげる。
美しい青空を何かが飛んでゆく。
鳥かと思いきや、雑誌だ。エロ本。兄が持っているやつ。ゴミ捨て場から、拾ってきたやつ。
兄が怒るとき、たいていそれを投げつける。
対抗するようにフライ返しが宙を舞う。これは母だ。時にはフォークやスプーンであったりもするが、今日はフライ返しが飛んだ。
いい加減にしろよ! 兄が言う。
それはこっちの台詞よ! 母が言う。さっさと働きに行ったらどうなの?
ああ、行くよ、と兄は言う。二度と帰って来ないかもな!
その捨て台詞が嘘であることを知っている。母と大喧嘩した兄は、友達やガールフレンドの家を転々としつつ、一週間後に必ず帰ってくる。今までに同じことが何度もあった。
母は深くため息をつく。食器をシンクに放り出し、何もかもアイツのせいよ、と毒づく。
アイツというのは、父のことだ。あたしが生まれた五年後に母ではない別の女とともにこの街を出ていった。
父なしの一家は借家を追い出され、トレーラーハウス暮らしを余儀なくされた。この人生の半分がこのトレーラーハウスで過ぎた。
しかし、それも今となっては過去の話だ。スクールバスの座席に似た硬いベッドはソファに変わった。頭上には無数の風船が穏やかな風にそよいでいる。
猫が瞼を舐める。ぬいぐるみのように抱き寄せると、にゃん、と嫌がって抵抗する。こら、静かにしなさい。あたしは言う。暴れると落っこちるわよ。
爪を立てられ、仕方なく手放す。生意気な猫が落ちてゆく。街の中へ。アーメン。
気を取り直して空中遊泳を続ける。
目指すは南。
ソファはすすむ。
あの日、五歳のあたしを置いて、父が消えていった道をなぞるように。