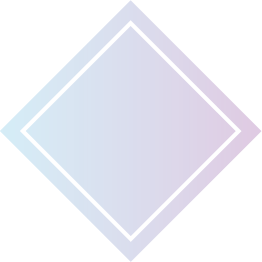……あれは泥酔で帰宅途中のFriday night
終電後の単線で、目の前を歩く人のかかとから、小さな火花がパチパチ飛んでいるのを見た。微かな風、チョーク粉のように宙へ舞い上がる。そのとき僕は会社の同僚と飲んだ帰りで、大分酔っぱらっていたので、思わず彼女の肩を叩いて「おや、貴女のかかとから……」と忠告せずにいられなかった。
振り向いたその人は長い睫毛を瞬かせて、急いで靴底をこすりつけた。萌黄色の外套が、闇に溶けて暗く変わる。肌寒い秋の風が吹きつけると、その人は首筋に手をあてて恥ずかしそうに目を伏せた。年若な女性の仕草だった。シニヨンに埋もれた星型のかんざしがちろちろと涼しげな音を立てる。
ハイヒールを響かせながら階段を下る。
ねえ。階段を下りた先で、その人は振り向いた。
「この辺、どうかしら? 住み良い処なのかしら?」
「近々、引越しの予定でも?」
「ええ、まあ……もう一つ、候補があるのですけれど」
「僕は気に入っていますよ。都心まで電車で一本だし、商店街が近くにあるから生活するのに困らない。地価も安いですしね」
「いいえ、利便や値段のことなどどうでも良いのです」
その人は再び歩き始める。その背中が捨て置けなくて――酔っていたせいもあるけれど――僕は跡をついていった。
ポプラ並木を歩く二人にシロクロの月光が降り注ぐ。屋根の上で黒猫が鳴いている。隣から見たその人の顔は、どこかで見たことのあるような気がした。ハイヒールの靴音を聞きながら、記憶を巡らすこと数秒。やがて僕は行きついた。
それはバンドのボーカルだ。高校生のころ好きだったロックバンドのボーカリスト。今でこそ熱は冷めてしまったが、十七歳の僕の世界は彼女の歌声でできていた。今ごろ何をしているのだろうか、延々と歌い続けていくように思えたけれど。
「私が気になるのは、流れ星公園のことなのです」
僕たちは街の外れにあるささやかな雑木林を歩いていた。骨ばった白樺の梢と赤煉瓦の遊歩道。黄色い火を噴く街灯が、棒のように立っている。「流れ星公園」という名の林は、読んで字の如く流れ星がたくさん降ることで有名だ。墨を塗りたくった空に、白い星が何千何万と浮かぶ。
「ここに住めば一人の夜も寂しくならずに眠れます」
「御冗談を。国有地ですよ」
「私、星の傍で暮らしたいの」
その人が一つ瞬きをすると、流れ星がたくさん降ってきた。道の途中にある木製ベンチに腰かけ、北極星を仰ぐ。そのうちに、引っ越す予定のあるもう一つの候補が気になったので、そのように尋ねると「ウユニ塩湖」と答えが返ってきた。
「ウユニ塩湖、知っていますか? 塩の積もった広い湖がどこまでも続き、水位の浅い水面はすべての情景を反射します。夜になると星空が映って、合わせ鏡の宇宙に立ったよう。それは素敵な眺めです」
合わせ鏡の宇宙を想像してみるけれど、上手くヴィジョンが出てこない。
「それはどこの国にあるのですか」
「ボリビア」
「人が住めるものですか」
「分かりません。けれど、お部屋の管理人が、早く決めてしまいなさいと催促してくるものですから」
「生活が逼迫しているのですか」
「そういうことではありませんけれど……」
流星が一つ残らず流れてしまうと、マッチの灯が消えるようにその人の姿も消えてしまった。
きっと僕は悪いことを言ってしまったのだろう。
その晩、明け方まで調べ物をしていて分かったこと。恋い焦がれていたバンドのボーカルが数年前に引退していたこと。その原因がほとんど自殺みたいな死にあったこと。
最盛期の急逝に、さまざまな憶測がメディアを飛び交ったそうだが不思議と当時の記憶はない。彼女の死があっけなさ過ぎて、僕の頭が夢の中のできごととして処理してしまったものかも知れない。
生前、彼女は自分の人生を星に例えていたという。
土曜日の朝、テレビをつけるとニュース番組で隕石の報道をしていた。ボリビアに墜落した隕石は大気圏に突入する前も1メートルほどの大きさしかなく、辺りの景観に支障は出なかったという。なるほど。
夢落ちる束の間、ウユニ塩湖を想像すると今度は確かに思い描けた。合わせ鏡の宇宙の真中、ハイヒールのかかとがチカチカ光るのを。