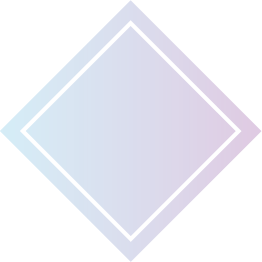「片手を一晩貸してやってもいいよ」
そう言って僕の大好きなみよちゃんは背負っていたランドセルを地面に置くと、左の片手を、まるで腕時計でも外すように外した。
みよちゃんの手は僕と同じくらいの大きさで、掌がちょっとだけ汗ばんでいた。新品の鉛筆ばかりが並んだペンケースみたいにきちんと揃った五本の指の、いちばん左の小さな爪にはショッキングピンクのマニキュアが塗られている。
みよちゃんには五つ年上のお姉さんがいるので、昨日の夜にお洒落のおすそ分けをしてもらったのだろう。
「あたしの片手、ちゃんと返せよな」
みよちゃんは僕にくれなかったもう一つの手で器用にランドセルを背負い直すと、校庭を走り抜けて行った。
僕はいつも置き勉をして帰っているので、ランドセルの中は空っぽだ。それでもみよちゃんの手が、ランドセルの金具にぶつかって傷ついてしまっては大変なので、着ていたTシャツを脱いで丁寧に包んだ。
白いランニングシャツに短パン姿となった僕は一昔前の小学生みたいだ。放課後の娯楽が、虫取り網でとんぼを捕まえることと、駄菓子屋で五円のチョコレートを食べることくらいしかなかった時代の人みたいだ。テレビも携帯も妖怪ウォッチもないなんて、考えただけでもゾッとする。
玄関のドアを開けると同時に僕はランドセルを放り投げようとして、慌てて思いとどまった。危ない危ない。鳥籠でも置くみたいにそっと身体の隣に置いた。
ゆっくり靴を脱ぐと、両腕にランドセルを抱いて、そろそろと階段を登る。キッチンからお母さんの声が聞こえるけれど、返事をしている暇はない。部屋の鍵を閉め、海賊船みたいなベッドの上に飛び乗ってようやくみよちゃんの片手を取り出すことができた。
いつもよりゆっくり下校したつもりだったけれど、揺れが激しかったのだろうか、みよちゃんの手はぐったりしていた。指先が、心なしか血の気を失っているように見える。枕の上にそうっと置くと、僕はゲームをセットしながら、みよちゃんの様子をうかがった……いや、みよちゃんではなくみよちゃんの片手の様子を。
みよちゃんは――今度は片手じゃなくてみよちゃん本体のことだけど――あんまり可愛い方じゃない。少なくともクラスにはみよちゃんより可愛い女の子がたくさんいる。性格も男勝りで生意気だ。女の子らしい部分が一つもない。きっとクラスの男たちの中でみよちゃんのことを好きな子は一人もいないだろう、僕一人を除いては。
僕がみよちゃんに惚れているのは、一つは思い切りの良い彼女の性格もあるけれど、大部分は彼女の持つ特別な才能に起因する。
みよちゃんの才能、それは誰よりもゲームが上手なことだ。学校一、地域一、いや日本一。もしかしたら世界に通用するかも知れない。とにかくみよちゃんはすごい。
コントローラーを握っただけで瞬時にゲームの操作法を理解し、当たり判定の基準を予測し、クリアのための最短ルートを導き出す。彼女の強さはRPGでもシューティングでもアクションでも変わらない。僕らゲーマーの間では「初見クリアのみよ」との異名で呼ばれている。ゲームセンターで遊んでいると、ときには大の大人が、みよちゃんにゲームの指南を乞いに来る。
なんてカッコイイんだ、みよちゃん!
僕が片手を借りたのも、一ヵ月間悩んでもクリアできないゲームを、みよちゃんに手伝ってもらうためだ。決してやましい理由はない。だいたい、女の人の手や腕の一部で興奮できる男なんているわけがない。いたとしたらとんだ変態野郎だ。全世界の女性の敵だ。
そういうわけで、僕はコントローラーを取ると、みよちゃんの手に握らせた。そこで根本的なことに気づいた。
パソコンならともかく、片手でテレビゲームはできない。いくら最強ゲーマーのみよちゃんでも、物理的な障害があればクリアなんてできっこない。そう思っていたところへ、突如としてコントローラーが頬に当たった。
ぐりぐりと、みよちゃんの片手がコントローラーを僕の頬へ押しつけてくる。ゲームはもう始まっていて、数々のゲーマーを泣かせてきた、鬼畜ステージで有名なボスがラッパ型の拳銃をこちらに向けている。Bボタンでみよちゃんは攻撃を回避した。すぐさまPAUSEすると、グーで僕の頭を叩いた。
間違いない、みよちゃんの片手は怒っている。指先がこう言っている。
「ええい、何をぐずぐずしておるか。早急に拙者を助太刀せよ」。
「ごめんよ、みよちゃん。今回だけは無理だ。どうやってもクリアできない」
「貴様、拙者を何と心得る。初見クリアのみよであるぞ」
どうして時代劇のような話し方なのか分からない。
「少なくとも、僕にそんな大役は無理だ。だいたい一ヵ月かかっても倒せなかった敵に今さら勝てるわけがない」
「男子たるもの泣き言を言うでない!」
みよちゃんの強烈な張り手が僕を襲う。このままだと、テレビより先に僕がゲームオーバーになってしまう。
「できないと思うからできないのだ。拙者は常に勝利だけを考えておる。これはプログラムとの戦いではない。プレイヤーと作り手の、一対一の真剣勝負なのだ。ゲームに負けるのは、貴様が己の力を信じていないからだ。難解なアルゴリズムに見えても、所詮は人が作ったもの、同じく生きた頭脳を持つ我々に打破できぬわけがない!」
筋肉脳の精神論者もびっくり発言。言っていることが滅茶苦茶だ。けれども、その真摯な言葉は僕の胸を打った。いや、尻を叩いたというべきか。
とにかくコントローラーを握れば、怒れるみよちゃんの物理攻撃を受けずに済む。やらなくて殴られるより、やって殴られた方がいい。みよちゃんはコントローラーの左側を操作し、僕は右側を受け持った。
PAUSEが解かれ、時が動き出した。
ボスステージにふさわしい張り詰めたBGMが部屋に響いた……。
僕たちは朝の早い時間に教室で待ち合わせをした。お母さんには部活動の早朝練習があると言って抜け出した。
ランドセルには、僕の部屋で一夜を過ごしたみよちゃんの片手が入っている。
教室の扉を開けると、一足先にみよちゃんが来ていた。彼女の片手には本当は持ち込み禁止のスマートフォンが握られている。三日前に始めたパズルゲームをもう最強データにしてしまったらしい。スマートフォンのゲームは終わりがないので張り合いがない、とみよちゃんは言った。
片手を取り出すと、彼女は長袖をまくりあげて、ぽっかり空いた丸い空洞にカチリと片手をはめ直す。不思議と、その一連の仕草がとても女の子らしく見えた。頭の中に口紅を塗る大人の女性やストッキングを履く女性の姿が思い浮かんだ(どこで目にしたのかは秘密だ)。
「簡単だったろ?」と、一夜ぶりに片手をぶらぶらさせながら、みよちゃんは笑った。
「あたしの手にかかれば、どんなゲームもお手のものさ」
遠くからクラスメイトの足音が聞こえる。二人きりの時間はあっという間だ。
思わず、言わずにはいられなかった。
「みよちゃんの、そういところが大好きだ!」