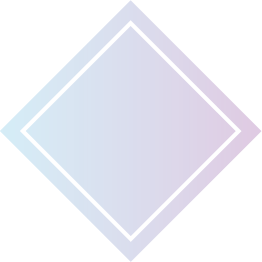ゴミ清掃員の男が、ゴミの中から女を見つけた。
それは真っ赤に燃えさかるような明け方のことで、日ごろの彼は睡魔やストレスと闘っている時間帯なのだが、その日はいつになく清々しい気分だった。
女は家庭用廃棄物の黒いビニール袋に埋もれるようにして眠っていた。ゴミ清掃員の男がゴミの中から引っ張り出すと、彼女は一糸まとわぬ姿で、さびた鉄と使い古された毛布の入り混じったようなにおいがして、美人だった。
透き通るように色が白く、男好みのスタイルで、髪の毛は黒。男は彼女を助手席に寝かせると、頭のてっぺんからつま先まで、繰り返し何度も眺めた。見れば見るほど、美しい。完璧だ。男は欲情した。
ゴミ収集の仕事を終えると、男は女を家に持ち帰った。バスルームできちんと身体を洗ってやり、髪の毛をドライヤーで梳かし、下着をつけさせた。薔薇の花が左胸に刺繍された白いブラジャーとショーツ。これは二日前に男の恋人が忘れていったもので、バストの形もヒップのサイズも彼女にぴったりだった。
完璧だ。
男は惚れぼれしながら、その日は一日中彼女を眺めて過ごした。
ラビッシュ(ゴミ)なんて冗談みたいな名前を持った女は、ずっと前からそこにいたみたいにすんなりと、男の生活に溶け込んだ。まるでベッドの下にうずまったまま、長い間忘れ去られていたジーンズみたいに。
ラビッシュのお気に入りはリビングにある赤いソファだった。朝はソファの上から仕事に出かける男を見送り、夜はソファの上で男のゴミくさい身体を癒した。真夜中に男がひっそりと煙草をふかし始めると、ラビッシュは男の腿ももに零れたわずかな灰を舐めながら、
「これ、もういらないのよね?」
灰皿の中に埋もれていた吸殻をつまみ上げると、その小さな唇に押し込んでしまった。もぐもぐ、ごくり。男がたった今吸い終わったフィルターも、火種ごと、ぱくり。空になったアメリカンスピリットのソフトパッケージまでもが彼女の胃に収まると、男はますます彼女に情欲を覚え、煙草くさいキスをした。
ラビッシュはいつでも美味しそうにゴミを食べた。煙草の吸殻、コーンフレークの空き箱、ビール瓶、刃零れしたカミソリ、切り終わった爪のカス。実によく食べた。男の家からはゴミというゴミがあらかた一週間でなくなり、床は塵一つ見当たらない。ラビッシュがゴミを口にするとき、決まって男は欲情した。いっそのこと自分を食べてほしいとすら願うようになって、冗談めかしてそのことを言うと彼女はひどく真面目な顔つきで首を振るのだった。
「わたしはあなたにとって不必要なものだけを食べるのよ。あなたを食べてしまったら、わたし餓死しちゃうじゃない」
それなら少しでも自分から出たゴミを食べてもらいたい。男の指はいつも深爪、髭も毎朝欠かすことなく剃った。
連絡がないのに業を煮やして男の元に恋人がやって来たのは、ラビッシュと暮らし始めて二か月が過ぎた頃だった。
その日は国民的な祝祭日で、男は朝からラビッシュとソファの上でいちゃついていた。
何時間とかけて別れ話を進めるよりも、説得力のある偶然の邂逅。男は罪悪感より先に、神のいたずらに感謝した。
「あの女の子はだれ?」
「昔の恋人だよ。だけどもういいんだ」
「あの人のことは、もういらないのね」
「そう」
肩を怒らせて部屋を出て行く恋人の背中を、ラビッシュが追い掛けた。
遠くから悲鳴が聞こえたような気がしたが、心地よい疲労感に満たされ、ソファから立ち上がる気も起きなかった。男が再び目覚めたのは六時間後のことで、窓の外は真っ暗だった。隣ではラビッシュがぐっすりと眠っていて夕食に起こすのも忍びないくらいだったが、男はいつも以上にすっきりとした頭で、ラビッシュは腹いっぱいに違いないと考えなおした。
ラビッシュと暮らし始めて半年が過ぎ、一年が過ぎた。
その年の冬は例年より早く雪が降り、男はたちの悪いはやり風邪をこじらせた。何日も物を食べられない日が続き、男の身体は衰弱した。朦朧とした視界の隅ではラビッシュが忙しく行ったり来たり、食べ物を探し歩いていた。
ラビッシュは空腹に困り果て、男に訴えた。
「食べるものがなくなっちゃったわ。生ゴミも使い古した歯ブラシも、全部食べてしまったのよ。ねぇ、わたしどうしたらいいの。あなたがベッドから片時も動かないせいで、わたし、食べるものがなくなっちゃったじゃない」
いつもは小川のせせらぎのように透き通ったラビッシュの声も、この日ばかりは外の木枯らしと同様、ひどく味気なく、男の心を凍えさせた。食べるものがない、泣きそうな声でラビッシュは繰り返す。
食べるものがない。食べるものがない。食べるものが、まったく、何一つ、ないのよ!
ラビッシュの手を振り払おうとした瞬間、男の薬指にはめられていたシルバーリングが床に転がり落ちた。それは去年のクリスマスに恋人から贈られたもので、月桂樹の葉のレリーフが巻きついた、泥棒すら見向きもしない安物だった。男の方も同じデザインの金の指輪を贈った。二人で示しあわせて、交換したのだ。
ラビッシュが床に落ちた指輪を拾い上げ、まるで飴玉をもらった子供のように瞳を輝かせた。
「これ、もういらないのよね?」
男は額から血の気が引くのを感じた。後悔が絶望を纏って頬を強く打った。
恋人に会いたい、と男は思った。
暗闇に立たされたまま、まったく前が見えない。涙すら流せない。自分がどこの誰かも分からない、孤独の深淵に立たされて、狼狽するタイミングさえも失った。
なんて自分は愚かだったのだろう。どうして彼女の悲鳴を、耳を撫でるから風のように、気にも留めなかったのだろう。思えば、あの女はいつだって俺のことを想ってくれたじゃないか。仕事終りのわずかな時間を割いて、会いに来てくれたのは誰だ? 毎週かかさず電話をくれたのは誰だ? いつだったか熱に浮かされた俺を、夜通し看病してくれたのは誰だ……?
男の目に涙が溜まって、指輪を舐めるラビッシュの顔がぐにゃりといびつに滲んだ。
返してくれ、と男は言った。
「ラビッシュ、指輪を返してくれ。今まで君にあげたものを全部、返してくれ。あのときはいらないように思えたが、本当はとても大切なものだったんだ」
「大切なもの? 心の底から大切に思うものは、そう簡単には手放せない筈でしょう。あなた、この指輪を放り投げたじゃない」
「ラビッシュ、返してくれ……」
「あたしに餓死しろって言うの? あたしと指輪、どっちが大切なの?」
「頼むよ……」
ラビッシュは男と指輪を交互に何回も見定めていたが、やがて、ふっ、と疲れたような息を吐くと男の左薬指に、ひどく慇懃な動作で指輪をはめてやった。リングが再び手に戻ると、緊張の糸が切れたのか、男は急激な眠気に襲われた。それだから、ラビッシュのひと言は耳たぶを撫でる風のように、頭の中へ上手く入ってこなかった。
その指輪は、あなたにとって食糧と同じ。愛を貪るためのもの。空腹が満たされれば、ゴミとして捨てられる。
あなたは食べるだけ。決して育もうとしない。
長い眠りから目を覚ますと、ラビッシュの姿は部屋のどこにも見当たらなかった。
熱は引いていて、男の手にはまったシルバーリングが冷たく光った。
次の日、病による長い不在を埋め合わせてくれた同僚に電話口で感謝の意を伝え、男はゴミ収集の仕事に出かけた。
朝焼けに目を細めながらゴミ収集車を運転していると、あるゴミ捨て場に女が捨てられているのが見えた。それは一年前に別れたはずの恋人だった。一糸まとわぬ姿で気を失っている。
気がつけばゴミの山はどれも、自分の家にあったインテリア。テレビ、机、雑誌、ビデオ、洋服……懐かしい感じがしたが、不用品は朝の外気にさらされて冷たくなったまま、既に誰のものでもなくなっていた。
腕の中で恋人が目覚めると、男は彼女を抱きしめ、自分がいかにみすぼらしい日々を送っていたか、いかに君が恋しかったかを思いのままに述べた。君がいないと耐えられない。俺の人生は破綻してしまう。そのせいで、ひどく辛い思いをした。俺には君の愛が必要なんだ。
目覚めた彼女は寝ぼけ眼のまま、男に向かって手を差しのべると、
「指輪。あなたに贈った指輪を返して」
男の指からシルバーリングを外し、ひょいと口の中に放り込んだ。
もぐもぐ、ごくん。
ああ、美味しい。
恐らく、空腹に耐えられなかったのだろう――かつて左薬指に輝いていた金の指輪も、彼女の空っぽの胃の中におさまって、今では見る影すらない。