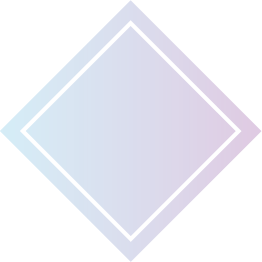スタンリー中央銀行に強盗が押し掛けたのは、先々週の金曜日だった。
「Head to the ground!(床に伏せろ!)」
どすの利いた男の声が店内に響いたかと思うと、顔を黒いマスクですっぽりと覆った男が三人、各々手に銃を持って飛び込んできた。皆、灰色のダウンに薄汚れたジーンズ、足元は白いスポーツシューズ。絵に描いたようなプライバシー防止ファッションの強盗団だった。受付嬢のキャーッ! という悲鳴を威嚇発砲で黙らせ、強盗は再び、先ほどのセリフを繰り返す。床に伏せろと言っているんだ! 俺を怒らせたいのか!
その場にいた十数名の客は、おそるおそる床に伏せる。ハロルドも例にもれず、両手を頭の後ろで組み、地面に膝をついた。早くも彼の頭の中は、今朝笑顔で見送ってくれた家族の顔が走馬灯のように浮かび上がってきている。妻のアンジー。双子の息子・リチャードとドン。小さいメス犬・アイリーン。運が悪ければ、彼らに二度と会えなくなってしまうかもしれない。そう考えて、ハロルドは小さく身震いした。
どうしてこんなことになってしまったんだ。どうしてこんなことに……
ハロルドは至って真面目な銀行員だった。この銀行に勤めて10年ほど経つが、その間に遅刻をしたのは2回(一つは、双子の息子の生まれた日、もう一つは叔母さんが車にはねられた日)だけ。欠席は1回(車にはねられた叔母さんが死んでしまった日)だけ。労働者の鏡のような人物であった。仕事ではたまにミスをするがそれは許容の範囲内。せいぜいお金を1ドル数え間違えたくらい。万年平社員であるが、今の給料には十分満足しているので、昇格届は出さずにいる。上司から見ても、ハロルドは絵にかいたような優良銀行員であった。
ハロルドは小さい頃から人並み外れない、ごく平均レベルの学力の持ち主であり、ごく平均レベルの学校に通い、輝かしい青春を―もちろん、ごく平均レベルで―謳歌し、大学を出てすぐにこの銀行に就職した。
それから10年。ずっとスタンリー中央銀行に尽くしてきたと言うのに、どうしてこんな目に遭わされなければいけないんだ。
「おい、お前。メガネの銀行員。そこのオヤジから鍵を貰って、金庫を開けろ」
パニックの余り、生まれてきてから今までの回想にふけっていたハロルドに、くぐもった男の声が届いた。ハッとして辺りを見回すと、黒い覆面をした強盗が彼を見下ろしている。
しがない銀行員のハロルドは、その時13番カウンターのすぐ後ろにしゃがみこんでいたのだが、丁度強盗の視界にバッチリと映ってしまったのだった。
「そうだ。そこのお前だ。早く後ろのオヤジから鍵を受け取れ」
ハロルドが振り返ると、そこには長年眼にしている小太り上司、ジミーの姿があった。ジミーは怯えた眼で手にした鍵をハロルドに差し出している。
「早くしろっ!」
強盗に急かされながら、ハロルドは鍵を受け取った。そしてそのまま強盗に連れられて、スタンリー中央銀行の奥にある何億ドルという金が詰まっている金庫室へと足を向ける。金庫の扉は鍵と銀行員のIDカード、合証番号の入力によって開扉される仕組みとなっていたが、何度も扉の開閉を行ったことのあるハロルドは、いとも簡単に超合金の扉を開けた。心の中では相変わらず、どうしてこんなことになってしまったんだ……と呟きながら。
そこで待て、という強盗の指示に従ってハロルドは超合金の扉の脇にひざまずいた。強盗は手にしたハロルドのIDカードから次々と顧客ボックスを開いていく。お目当てはボックスの中にある、誰かの全財産だ。ヒャッホーイ! と歓喜の声をあげながら強盗は手際よく手にした袋の中へ札束を詰め込んでいく。
ハロルドは冷たい床に身体を押しつけながら、自分の運命を呪った。
どうしてこんなことになってしまったんだ。どうしてこんなことに……。
このまま強盗が金を持って逃げてしまえば、スタンリー中央銀行は大損害を被るだろう。銀行員がこつこつ積み上げてきた顧客の信用も一気に地に落ちてしまう。運が悪ければ、スタンリー中央銀行は倒産してしまうかもしれない。少なくとも、金庫の鍵を開けてしまった僕に、責任の一端が降りかかってくる事は間違いない。
どうしてこんなことになってしまったのだろう。僕はいつだってこつこつと真面目にやって来た。それをこんな連中に、一瞬にして叩き壊されてしまうのか。僕が積み上げてきた努力や幸せや堅実な生き方は、そんなにもろいものなのか。いましがた出会ったばかりの強盗に易々と崩されてしまうくらい。
僕の人生は、一体なんだったのだろう……?
「うッ!」
小さな悲鳴がハロルドの耳に届いた。それは金庫の中にいた犯人のものに違いなく、ハロルドは反射的に金庫の中を覗き見る。何百枚という札束がひらひらと金庫の中を舞っていた。それも数秒で全て地面に落ちてしまうと、乱れた札束の中から覆面マスクに隠された強盗の顔が浮き上がって来た。強盗は仰向けに倒れていた。ぴくりとも動かない。この可哀想な犯罪者は、足元に転がっていた紙幣を踏んづけたか何かして、滑ってしまったのだった。うちどころが悪かったのか、強盗は気絶したまま暫く起き上がりそうにない。
ハロルドは彼の傍に近づくと、強盗が意識を取り戻す気配のない事を入念に確かめた。そして、自分の着ていた営業マンの典型のような流行を超越したデザインのスーツを全て脱ぎ捨てると、強盗のボロのダウンやジーンズを身につけた。強盗の洋服からは、都会の片隅でよく嗅ぐ、ホコリとゴミの臭いがした。念を入れて、強盗に自分のスーツを羽織らせる。最後にハロルドは強盗の頭から、彼のアイデンティティとも言える覆面をはぎ取って、すっぽりとかぶってしまった。
その時、金庫の外から見知らぬ男の囁きが聞こえた。
「ダニエル、早くしろ! カネは詰め込めるだけでいい」
「ああ、すぐ行くよ」
ハロルドは彼の声に似せたくぐもった声で返事をすると、サンタクロースのお爺さんのように布袋を担ぎあげ、札束にまみれた金庫室を後にした。
スタンリー中央銀行に、強盗が押し掛けた先々週の金曜日、
ハロルドは自分の生き方を変えた。