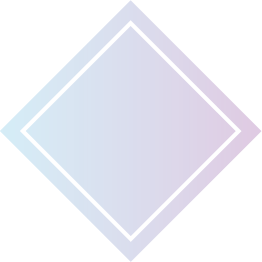殺し屋・五六の死の知らせは、界隈に住まう者にとってただならぬ衝撃を与えた。誰もが耳を疑って、長袍あるいは袈裟あるいは礼服あるいはメスドレスの使い番へ掴みかかると口角泡を飛ばして事件の真偽を問いただした。
答えはYESそしてNO。
真を確かめる者と偽を疑う者とによってメッセンジャーの返答は真っ二つに分かれたが、どちらにせよ、殺し屋・五六は二月二十九日午前五時零六分にこの東京から一瞬にしていなくなってしまったことは動きようのない事実であった。
「五六が最期に感じたのは舌を焦がす灼熱の炎。口腔から射入し後頭部へ射出された20ゲージの弾丸は0.003秒のうちに豪傑・五六の生命を奪うに十分だった」
界隈に住まう者たちは、五六の亡骸を見たがった。というのも、彼らはもちろん仕事の依頼主でさえ殺し屋の生前を知る者はいなかったからである。
風来人の五六はどの組織にも贔屓を持たず、依頼を受ければ平等に仕事をこなした。ひとたび五六に目をつけられれば、標的の命は三日と持たなかった。組織の幹部だろうが場末のチンピラだろうが政界の老議員だろうが花屋の娘だろうが例外はない。生命は皆平等に扱われた。
そのあまりの手際の良さに、五六の仕事は一種の生理現象、晴れていた空が俄か雨に見舞われることと同じだと考える者も少なくなかった。中には五六の死を契機に「死」の概念がなくなったのだと主張する者までいた。
「五六の骸は請負人の手によって東京湾からさほど遠くない雑居ビルの跡地に埋葬された。その場所は我々にも分からない」
新しい時代の幕が開けた。朝陽の昇りきる前に一人の殺し屋が現し世から滅されたことで、界隈に住まう者たちは俄かに判断基準を失った。誰を憎んでいるのか、どの程度の憎しみが殺しに値するのか、そもそも憎しみとは何か。
五六によって隔てられていた生と死の垣根が取り外された今、この状況は安泰なのか危殆なのか判断がつかない。振りまいた小麦粉の中で銃を発砲できないように、五六の死の残滓が覆い尽くすこの街において、彼らの為す術はただ指をくわえてじっと日出を待つ他ない。
「五六は当然の報いだと言っていた。それが自身に向けた言葉なのか他者に放たれた言葉なのかは各人の判断にお任せしたい」
喪に服した東京湾景にただ一つの疑問が残った。すなわち「五六を殺した手練は誰か!」。
界隈に住まう誰もが話の最後に長袍あるいは袈裟あるいは礼服あるいはメスドレスの使い番の裾に縋りついて真相を乞うた。台湾に向けて出港する船の船首に佇む彼らの声は波の音に掻き消され、呆然と品川埠頭に立ちすくむ人間の、数多の銃声に麻痺した耳にはその言葉の片鱗さえも届かなかった。
「五六を殺したのは五六自身だ。彼女は平生の如く、その依頼に答えたまでだ」