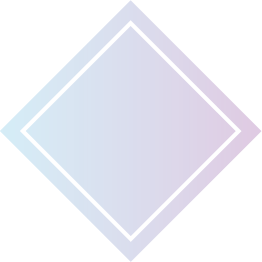老舗の大型デパートの回転ドアをすり抜けると、薄ら寒い風が肌を掠めた。女はコートの襟を立てる。両手指をすり合わせながら、急ぎ早に横断歩道を渡った。このビルで化粧品をいくつか購入しただけなのに、ビルの合間からちらりと覗いている空は情熱的な赤色に燃えている。何もすることがないと、時間の感覚が狂ってしまって厭だわ、と女は思った。
彼女がデパートに入ったのが開店直後の十時だったので、優に8時間は店内を彷徨っていた事になる。それでも約束の時間にまだ間に合うのは意外だ。こういう時にこそ、自分に授けられた時間の膨大さを自覚せずにはいられない。果たして、「余りありすぎる時間」というのは自分に幸せをもたらすのか否か。もしかしたら倦怠と退屈しか残さないのではないか。
そんなことを考えている間に、すぐ約束の地というものに行き着いてしまった。デパートから駅を挟んで反対側にあるのだから無理もない。
この、形は他の高層ビルと変わらないがどこか上品なたたずまいの建築物を眺めるたび、女は嬉しくなる。都会に出ればどこにでもありそうなホテルなのに、どうしてこんなに心が弾むのかしら、というほど嬉しくなる。黒い大理石のような壁が光の加減で白く見えたり、ゼンマイ螺子(ねじ)のような回転ドアの奥にシャンデリアの黄色が煌々としていたり。実のところ、それらがギラギラした目に痛い類の光ではないところに惹かれるのだ。
女がまだ愛らしい学生だった時分から、建物はずっとその場所にある。小さかった女は、遠巻きにその楼閣を眺めているだけで満足だった。若い、溢れんばかりの想像力でホテルの内装を思い描いたりするだけで幸せな気分になったものだ。将来、自分がこのホテルの常連客になるなんて、夢にも思っていなかった。
もうそろそろチェックインしてもいい頃ね、と女は思った。多少予約時間に差異があったって構わない。どうせ、金曜日の夜は予約が決まっているのだもの。ロビーにて、女は自身の名を名乗る。従業員とも顔なじみになっているためか、すんなりと部屋の鍵を渡される。部屋までのエスコートがないのは、立派な「暗黙の了解」だった。エレベータに乗る間際、女はロビーを隅々まで見回した。いつもの場所に牢のような電話ボックスがあるのを確認して、扉を閉める。
部屋に付くと、やはりそこは先週の金曜日と変わらない位置に机があり椅子があり、電灯はこぢんまりとしたシャンデリアだった。さすがにバスルームの鏡に書いた口紅の文字は消されていて、それを客室係がやったのかと思うと、女は少し恥ずかしかった。まだ約束には時間がある。早々に風呂に入って、髪の毛をドライヤーで乾かして、新しい化粧品を試したりした。植物性油のファンデーションは肌にどうのこうのと輸入雑貨の店員は説明していたけれど、本当に効果はあるのかしら、と女は思った。
女はよく「内なる声」というものに「~かしら」といういかにも女々しい言い方を用いた。別段意識しているわけではないのだが、どうも声に出さない独り言は、疑問形だと「~かしら」という終助詞がつく。それは、どうしてなのかしら、と以前考えたことのある女だったが、ここでも「~かしら」を用いてしまい、無意識の癖であるということが考えずとも分かった。反して、口頭では滅多に「~かしら」なんて、懐古趣味的な言い回しは使わない。
これは、一体どういうことなのかしら。
ソファにもたれ掛かり、ぼんやりと物思いにふけっていると、玄関ドアがノックされた。覗き穴を見ずとも、扉の向こうの正体は分かっている。女は壁にかかった時計を見る。きっかり二十一時を指していた。
「やあ」
いつもと変わらない挨拶でやってきた男は、女よりも一回りは年上で、あと数年もしないうちに初老に身を変えるであろう落ち着きと、経済的自由からくる余裕も兼ね備えていた。しかし、体の隅々まで精力が漲っていて、凛とした風袋からは年齢と比例する精神の衰えや疲れが微塵も感じられない。仕事主体の独身貴族というイメージが、彼の付けている香水の匂いくらいに強烈だが、しかし本当のところそうではないと女は感づいている。
「今日は、早いね。まだ来ていないかと思ったのに、ホテルマンが、もう君が部屋にいると言うんだ」
「買い物が、早くに済んだから」
「そう。友達は?」
「多分家にいるんじゃない。もう付き合いが長いから、お互いの生活に干渉したりしないの」
「そうなのか。君たちの年齢は、同居していてもそういう付き合い方をするんだったね」
「気心が知れすぎていると、どうしてもそうなるのよ」
「部屋は狭くない?」
「もうあのままで十分」
「そうか」
「ありがとう」
「こっちが好きでやってるんだから」
「うん」
口数が少なくなっていくと同時に、お互いの物理的な距離は縮んでいく。女は男の着ているコートの中に顔を埋めた。香水と煙草と新しいシャツの匂い。それらが混ざり合ってこの男特有の体臭を作り出している。女はこの乾いた匂いが好きだった。コートの中にこもった体温もコートの布ずれのごわごわした音も。女は男の作り出した世界に魅了され、からめ取られていくこの瞬間が狂おしいと思った。気が触れそう。この人、一体何なのかしら。人間ではないのかも。
よく分からない自問自答が頭に浮かんでは消えていく。これは一体、どういうことなのかしら・・・・・・・・。
初めのうちは分からなかったが、ちょっとした細かい所作から、男にはちゃんと家庭があるのだということが分かってきた。この男には仕事とは違う顔をみせる舞台がもう作られている。女とのひとときは、仕事と家庭の舞台裏であり、言ってしまえば一時休憩のようなものだった。男の、人生から脱線しないための、一時凌ぎ。女が住んでいるマンションは男によって維持されている、立派な妾宅だった。
わたしは、囲われているのかしら。そこにはいずれ終焉が来るけど、未来は来ないのかしら。わたしは、これからどうなっていくのかしら。子供でも作ってしまえば、少しは希望が見えたりするのかしら。女はそこまで考えて、自分の稚拙な戦略が馬鹿らしくなり、自問自答をやめる。そして男の腕の中で思ったのは、同居している友達も間接的にこの人にただ飯を食わせてもらってるのよね、悪い奴だなぁという、吹き出してしまうくらい平凡な常識だった。
零時近くなって、女はゆっくりと目を覚ます。男は隣でぐうぐういびきをかいて眠っている。肩が規則正しく上下する様が、私生活で男が演じている役割を無意識に呼び覚ましているような気がして、女は暫く彼の寝息を楽しんだ。この何の罪もなさそうに眠る顔が、今日は残業だとかなんとか、都合のいい事を言って最愛の人の目をごまかしていたりするのかと思うと、何だか男の弱みを握っているような気がして女は少しだけ嬉しかった。
起こさないように男の上を跨いで、自分のバッグから携帯電話を取り出し電源をつける。ほの明るいライトが点灯し、ディスプレイが映し出される。写真機能を立ち上げて、顔を男に向けた瞬間、新着メッセージが届いた。ずっとセンターに留まっていたのだろう、メールの送信日が昨日の朝六時になっている。
〝お前、空見た?〟
友達からの写メールには煌々と燃える朝焼けが映し出されていた。きっとあのマンションの近くから撮影したのだろう、画面の端に移っている高層ビルの形に見覚えがある。そういえば昨日の夜はあの子と寝たな、と女は思い出した。ペットのような友達との夜のひとときは誠実で正しいような気がした。これが、あるべき姿なのだと思った。正しいとか間違っているとか、そういう倫理観とは無縁の事柄なのに、昨夜のセックスは正しかったのだ。
少しだけ、自分の家と友達が恋しくなって、そう思うこと自体恋人に悪いような気がして、ろくに返信もせずに再び携帯の電源を切る。女は元の位置に戻って目を閉じる。現時点での幸せに身を投じるように、女は男に寄り添った。