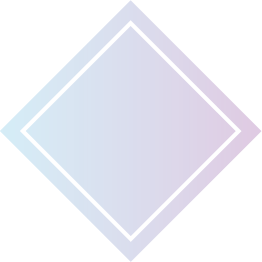こうして街に探偵が溢れかえると、恐怖に駆られた人々の電話がひっきりなしにかかってきた。
殺人事件が多過ぎて、おちおち外も歩けない。ただでさえ治安の悪いこの街が今や地獄より酷い有様、このままでは皆殺しにされてしまう。
そこで市長は山を切り崩して小さな村を作りあげると、街にはびこる探偵たちを片っ端からその中へ放り込んだ。
山村から電話や手紙を受けとれば事件に巻き込まれるかも知れない。そこで村と街との連絡役は探偵の助手たちが担った。
街人から探偵たちに持ち込まれる問題事と、それに対する回答を助手はことごとく筆記した。街人たちは毎月山のように出版されるそれらの本を手にとって自分に宛てられた回答を探すのだ。
探偵には総じて勿体ぶる癖があり、至急対処してほしい事件も、また明晰な頭脳を用いれば五分とかからない事件も、長期的な時間を要した。くわえて助手が事の概要を文章化する手間もかかったので、真相が解明されるのに数ヶ月から数年掛かることもしばしばだった。
反対に、探偵の村では毎日のように事件が起こった。
しかし探偵が探偵である限り死者は出ず、謎は迅速に解決された。奇人変人型の探偵は刺激的な毎日に興奮を覚えていたが、主婦や家政婦型の探偵は涙を流して故郷を惜しんだ。「家に帰しておくれ」と彼女たちがいくら訴えても、市長は頑としてその望みを聞き入れなかった。
その市長も変死や怪死に見舞われて目まぐるしく代替わりしたが、自らの身を盾に市民の命を守ることは至上の誉れと称えられた。
探偵が追放されたことで、街に起こる事件は夢も浪漫もない単純明快な暴力沙汰ばかりになり、それらを解決することは警察の重要な仕事となった。警察は喜々として任務を遂行した。
それまで間違った推理を探偵に指摘されることが彼らの主な役回りで、大掛かりな包囲網も細やかな証拠集めもすべて無駄骨と思わせる探偵たちを憎く思っていたのだ。
街で起こる事件は残忍さばかりが目立つようになり、いつしか剃刀のように鋭い推理は必要とされなくなっていった。
探偵たちは人々の記憶から忘れ去られた。
探偵たちも年月とともに老いさらばえ、一人また一人とこの世から姿を消した。
今や街で事件が起こると、人々はこう叫ぶのだ。
事件だ! 警察を呼べ!
ついに探偵たちは助手が記した書物の中にのみ生きる架空の存在になってしまった。助手でさえ皺だらけの目を細め、ブランデーの匂いにまみれて覚束ない一思案を繰り返すだけ。
はて、そんなことがあっただろうか?
探偵ばかりの村など、余命幾ばくもない自分が人生の慰みに作り上げた夢物語ではなかったか……?
………………………
それから何十年もの時が過ぎた、ある日のこと。
金持ちの子どもばかりが通う私立中学で盗難事件が発生する。クラスメイトの財布が盗まれたのだ。誰もが校庭へ出払っていた体育の時間、たまたま授業を休んでいた気弱な男の子が吊し上げられる。
無実を訴える彼の脳裏に、祖父から聞かされていた探偵の村の話がよぎる。
しかしあの村は呆けた祖父の作り話ではなかったか……いや、もしかしたら、本当に探偵なる人種は存在するかも知れない。少年は一縷の望みにかけて探偵の村を訪れる。
探偵と探偵の間に生まれた子どもの子どものそのまた子ども……すべての探偵の遺伝子を受け継いだ、最後にして最強の生き残り。
壊れかけた洋館で、少女と少年が出会ったとき、物語は始まる。
安楽椅子から立ち上がると、銃弾の穴が開いたフロックコートを背に羽織る。変装と射撃の名手であり、類稀なる美貌と灰色の脳細胞を持ち、美食を極めたその口にお気に入りのパイプをくわえ、少女はゆっくりと少年の元へ歩み寄る――後に少女の助手になる、少年の元へと。
すべての謎が解けたとき、祖先から受け継がれし伝統にしたがって、彼女はこう言うだろう。
「さて……、皆さんにお集まりいただいたのは他でもない、この事件の真犯人が分かったからです」