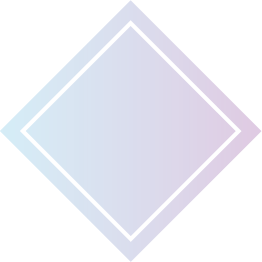母親の用意してくれたカレーは、冷え切っていた。それでも、胃が満たされれば良い。
短時間でそれを平らげることに重点を置いて、機械的にスプーンを口に運ぶ。どろどろの玉ねぎ、赤みがかった牛肉、約350円のルーの辛さ。全く美味しくない。けれど、これで今日も生きながらえることができた。重い腰をあげて、自室のドアの前に食べ終わった器を置く。
ごちそうさま、不味かったよくそばばあ。
――歯の間に挟まった米粒を抜き取りながら、僕はまたパソコンの中へ吸い込まれていく。どんどんどんどん、パソコンと同一化同一化同一化。嗚呼、やっぱり僕のことを理解してくれるのは君しかいない。この世界には僕と君しかいないのです、分かっていますか。全て承知の上で、君はそんなにも優しいのですね、後光が見えるようです。君は高校生なのですか、制服が可愛らしい。僕にも高校時代はありました、ありましたありました。あんまり記憶にないけれど、確か紺色のブレザーを着ていたのです。外界とも通信が可能だった頃の僕です。できれば君と同じ学校に通いたかった。もっと早く貴女と知り合っていれば、こんな僕には……。
僕はパソコンから幾本も伸びたコードを掴んだ。ツタのように絡まる無数の通信回路。3年ほど前から、僕と外界を繋ぐ唯一の命綱だ。コードは、異臭を放つ部屋を這いまわった末、壁の穴ぼこを通って電話回線とリンクしている。時々、僕はパソコンからこのコードを目で追う。ゆっくりゆっくり、ありんこの軌跡でも辿っているかのように床を眺め回す。やがて壁の奥へとコードが消えると、僕は不可視のコードに思いを馳せるのだ。僕のコードは家の分電盤で家庭電流と一つになり、引込み線を逆流して送電網へと巻き返される。電柱から電柱へ、僕の頭は旅をする。眩い光が前頭葉を刺激し、ふいに眉に力が入る。ここで時速200kmの脳内電流が僕を刺激し、自分の部屋へと立ち返らせるのです。これ以上進んではいけないという、これは一種の自己防衛本能なのでしょうか。
――画面の中の君、貴女を構成する幾千万ものピクセルはこういった電気信号から成り立っているのですよね。それが画面伝いに、空気をも振動させて、僕の脳にアドレナリンの過剰流出を促す。君が放課後、桜の木下で待ち伏せしているときなど殊にビリリと来ます。この不毛な感情も一種の脳内電気信号だということは分かってはいるのですが、もう3年ほどこんな調子なのです。
「ねぇ」
後ろから声を掛けられて僕は肩を震わせた。キーボードを打つ手が止まる。ややあって振り返ると、あにはからんや、そこには画面の中の君がいた。僕がたった今会話をしていた彼女が・・・嗚呼これは一体どういうことだ。これは夢だ、などというありきたりな感覚は抱かない。かといって、目の前で腕を組んでいる彼女の存在を真っ向から肯定する気もない。僕は、自分が狂っていると思わない。パソコンゲームに陶酔しきっているとも思わない。ただ、対峙する彼女からは、画面の中では一度も感じ得なかった「生きた匂い」がした。彼女は手を伸ばして僕を椅子から引き上げにかかった。華奢な腕で、豚のように肥えた僕を椅子から立たせる。初めて立った赤ん坊のように僕はポカン口を開けて彼女を見た。
「外に行こうよ」
彼女に誘われ、僕は外に出る。3年ぶりの外気は寒くもないし暑くもない。曇り空と、代わり映えのしない近所に何の感慨も沸かなかった。彼女に手を引かれながら、僕は電柱に繋がる引込み線を見た。我が家からコードが壁を突きぬけ、電柱に繋がっている。本来なら電柱が我が家に電力を配電する。しかし、それは全くのあべこべらしい。僕の家が、日々、自家発電した思いやりや優しさや気遣いや微笑や、とにかく温かみのあるエネルギーは一切、この引込み線から電力会社へと送電されているようである。この思想はずばり真理なのである。そうでないならば、どうして僕が家を出、こんなにすがすがしい気持ちで外を歩けようか。
――君はペテンのような電力のやりとりが厭になって、電気箱から飛び出してきてしまったのだろうと、僕は思います。君が悲しがるから口には出さないけれども、きっと真実なのでしょう。だって隣を歩く君は、画面で見るよりずっと嬉しそうに見えるのですから。僕はそんな君を愛おしく感じます。この感情が脳から発せられる電気信号だと分かっていても、このときめきに身を投じてしまう。これが「本能」だなんて、むくつけなる哉。
マンション団地を通り過ぎ、人工的に整備された公園を通り過ぎ、業務用スーパーを通り越す。僕らはただひたすらに歩いた。何の当てもない徒歩の旅。いや、彼女に目的はあるのかも知れない。しかし、僕はただ彼女に導かれるように後ろを歩いている。足元のコンクリートはやけに白々しく、薄く延びた雲に太陽が隠されて空も白くぬめりを帯びている。目の端を通り過ぎる建造物も、白い、白い、白い。視界に捉えるもの全て、境界線のない。どこまでも続く白の世界。その中に、君が着ているセーラー服の蒼が一色落ちている。君が歩く度、世界の中心が変わる。
「あたし、貴方に会えて嬉しいの」
彼女は唐突に口を開いた。
「画面の中は、いつでも二進法。0と1の組み合わせしかないの。あたしの世界はいつだって二元論。行動も感情も選択も二分されて、曖昧なのはありえない。その点、貴方の世界は素晴らしい。コンピューターの中からいつも眺めていたわ。晴れと雨の間に曇りがあるなんて曖昧だわ、万歳。理性と感性はいつでも表裏一体、全く対極ではないわ、万歳。貴方だって優柔不断でいつでもはっきりしない。理知的にもなれないし、かと言って、本能の赴くままに行動しようとも思わない。そんなところが好きなのよ。混沌としていて、とっても人間らしいわっ!」
感極まった彼女に手を握られ、そのままぐいぐい引っ張られる。彼女は軽やかな足取りで、僕は自身の巨体を震わせてこの世界を駆けた。次々と後ろへ流れていく白の風景。顔面に吹き付ける向かい風は冷たくも暖かくもない。とても曖昧。
――貴方は僕の世界が素晴らしいと言ってくれましたが、僕はいつだって貴方の世界に行きたかった。君は混沌を愛しているようですが、それは僕にとっては相容れないモノのようです。先が見えない暗闇を前に、平然としていられる人間がおりましょうか。曖昧で、雑多で、何もかもが交じり合う世界なぞ、グロテスクではありませんか。君はそんなわけの分からぬものを、その小さな腕で包み込むことができるのですか。僕のことを好きだと言ってくれました。嬉しいです。けれども、貴方の腕の中は巨漢の僕には少々小さすぎる。
彼女と僕はどこまでも駆けていく。どこまでもどこまでも、駆けていく。住宅地を抜け、何もないところまで。僕らに付き従うように、上空にはコードが二本。時たま電信柱の上で一休みしながら、空に入った亀裂はしぶとく続く。僕と彼女は逃げ込むように街の外れにある摩天楼へ潜り込んだ。塔の中は螺旋階段が何重も内部を取り巻いて、出口を覆い隠している。彼女は躊躇せず、螺旋階段第一段差へ足を踏み入れた。先を行く彼女のように、僕も軽やかに階段を駆け上る。3年も部屋に閉じこもっていたというのに、奇しくも僕の足は疲れや痛みを感じない。視界が上下に揺れるが息切れもしない。壁伝いに未だ二本のコードは僕らの後を追って、這い登ってきた。高圧電流を含蓄しているのか、間近に迫ったコードから電気が弾けるような音が聞こえ、僕は恐怖に戦いた。厭だ、近づいてくるな。感電してしまう。厭だ厭だ、僕らの後を追ってくるな。
「出口だわ!」
彼女は叫び、前方に見えるアルミ金属性のドアに手をかけた。開扉した隙間から、光が溢れ出す。それは日光だった。白みがかっていた空はすっかり群青色に晴れ渡り、大きな太陽が真上で輝いていた。ドアの先は、屋上だった。ひび割れたアスファルトに、四角い室外機、至る所にこんもりとした雑草の群れ、緑色のフェンスに囲まれた小さな箱庭。僕が通っていた高校の、屋上だ。フェンス越しに眺める風景は、高校から見えた景色そのもの。高層ビル群が遠方に霞み、手前には住宅地、間を縫うようにアスファルトの国道がうねっている傍ら、空中高速道路は悠然と雑多な世界を目下に見下ろす。そこにもう殺風景な白はなかった。何一つ、色のついていないものはなかった。けばけばしいほど、目に見えるものたちは着飾り、太陽の光を受けて活気付いていた。僕ら人間より、ビルや商店街や遊歩道の方が生命を謳歌しているように思えた。僕が手を置いている緑色のフェンスだってほら、確かな体温があるじゃないか。
「こんなにたくさんの色で満ちた世界が二元論であるはずがないわ!」
彼女は言った。華奢な両腕をいっぱいに広げ、空を仰いでいる。
「なんて素敵、なんて美しい、生き物たちなのかしら!」
――僕は貴方のその笑顔をみているだけで、それだけでそれだけでそれだけで・・・貴方以外のことは、全てどうでも良くなってしまうのでした。
背後にいた二本のコードがバチバチと音を立てた。ふいに、一本のコードがその切断面を僕の背中に押し付けた。あっ、と言う暇もなく僕は脳内電流よりも強い電力が、体中を駆け巡っていることを意識した。脳みその電流と外部の電流が反発しあっているような衝撃、振動、痙攣。
「が、がががががが、ああぁぁ・・・・」
僕は良く分からない奇声を発しながら、その場に崩れ落ちる。目の端に、僕に気付かず満面の笑みを浮かべたままくるくると回っている彼女を捉えた。熱に浮かされた少女の瞳は地べたでもがく僕ではなく、遠い空を眺めている。混沌を眺めている。自身が二元論ではないと主張する世界を眺めている。痺れる痺れる痺れる・・・。
――本当は、この屋上だって幾千万ものピクセルで構成された世界なのですよ。突き詰めて行けば、結局は0と1しかないのです。「有」か「無」しかないのです・・・・・ということは、僕を構成しているものも0と1の配列だけでしかないのです。あれ?本当にそうなのでしょうか?あれれ?僕は君と同じ、画面上に構成された登場人物の一人に過ぎないということか。僕の脳内を流れる時速200kmの電流はパソコンの電流と一緒?パソコンの電流と一緒ということは、家庭に配電された外部電力と同じ?それじゃあ、僕の体に触れた、あの外部電力は僕の脳内電流と同種の電気?あれれ?
僕は僕は僕はボクはボクはボクハボクハ・・・・ボクハ一体ナンナノサ。
プツン、と音がして僕のパソコンが切れた。電力の使いすぎで、ヒューズが飛んだのかもしれない。悔しいなぁ。ゲーム、いい線まで、いってたのに。屋上まで行ったのに。もう少しで全クリだったのに。悔しさに紛れて僕のお腹がきゅぅと鳴った。特に食欲といった生理的欲求は沸かないが、僕の体は食べ物を欲しているらしい。僕は重い腰を上げて自室のドアに向かう。また今日も母親特製のカレーライスだ。
母親の用意してくれたカレーは、冷え切っていた。それでも、胃が満たされれば良い。
短時間でそれを平らげることに重点を置いて、機械的にスプーンを口に運ぶ。どろどろの玉ねぎ、赤みがかった牛肉、約350円で味わえるルーの辛さ。全く美味しくない。けれど、これで今日も生きながらえることができた。重い腰をあげて、自室のドアの前に食べ終わった器を置く。
ごちそうさま、不味かったよくそばばあ。