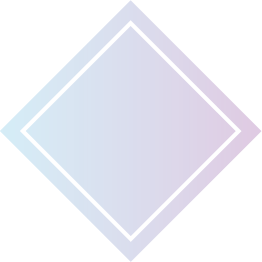ああ、とんでもない失敗作だ!
気づいたとき、博士の身体は線路の上に投げ出され、間近に電車が迫っているのでありました。
なんという皮肉だろう! 私の発明は電車によって生み出され、私の身体は電車によって死に還る!
K駅からS駅に向かう間の、トンネルをくぐりぬけて十三秒。
レールとレールの繋ぎ目に大きな溝があり、車両も人も飛び跳ねるようにガタン!
はずみで、自分の身体から何か得体の知れないものが飛び出していったことに、博士は気づきました。博士は人類の歴史の中でも一二を争うほど優れた頭脳の持ち主でしたので、内臓の動き、血液の流れ、細胞の数を常に把握していたのです。
一体何が飛び出したのだろう。研究所へ戻って調べるに、「電界」であることがわかりました。人の身体を取り巻く電気の流れのようなもの。電車が揺れることによって体から電気が放出されてしまうのです。
なんて勿体ないエネルギー。どうにかして有効利用できないものか。
博士は「電界」を動力に変換する装置を発明しました。それをロボットに埋め込むことにしました。七十歳を過ぎても博士は独り身。身の廻りの世話をしてくれる召使が欲しかったのです。
土曜の朝六時半、高架上で博士は電車を待ちました。その時刻の電車にはたくさんの女学生が乗っていました。殆どの会社はお休みだけれど、体の良い女学校はキチンとあるのです。眠い目をこすりながら女の子たちを乗せた電車は――ガタン!
「電界」は身体を離れ、瞬く間にロボットに吸収されていきました。
ビリビリビリ、ロボットの身体に電流が走ります。鋼鉄のまぶたが重々しく開きました。
「お前は私の召使だ。言われたことをキチンとするんだよ」
ロボットは頷きました――「承知シマシタ、旦那サマ」。
ところがこのロボット、全く使い物になりません。
大事な書類にコーヒーをこぼしてしまうし、実験用の白衣にはアイロンの焦げ跡がくっきり。お料理も、洗濯も、難しい計算もできません。窓辺に腰かけては日がな一日空ばかりを見上げています。電流の貰いどころが悪かったのだと博士は気づきました。
一ヵ月経っても、ロボットは何もできませんでした。博士は時期に苛々してきました。
「この役立たずめっ!」
力任せにロボットを殴りつけますと、鉄の頭がパカンと響いて、痛みを感じるスイッチに電流が流れました。ロボットの目からはぽろぽろと水が。
「痛イワ……。痛イワ……」
博士は胸のすいた心地がしました。途端、頭に新しい閃きが生まれました。良い研究を思いついた! 博士は研究室に飛んでいって、実験の準備を始めました。
それからというもの、博士は研究に行き詰まるとロボットの頭を殴りつけました。ロボットの目に涙が溢れます。
「痛イワ……。痛イワ……」
なよなよと床に崩れ落ちるロボットを見ていると、不思議と博士の頭には新しい発明がどんどん浮かびました。全自動料理マシン、全自動洗濯マシン、全自動掃除マシン……博士はそれらのマシンに家事をさせました。そして新しい発明が思いつかなくなると、机を叩く貧乏ゆすりのようにロボットの頭を叩きます。パカン!
博士に叩かれた晩、ロボットは勝手口のドアの外でしくしくと泣きました。泣き声を聞きつけた博士がまた一つパカンとやると、声を押し殺して泣きました。
博士が叩き過ぎたからでしょうか。頭の導線が少しずつねじれて、痛みを感じるスイッチに電流が流れたまま元に戻らなくなりました。ロボットは「キャア!」と叫ぶと研究所を飛び出し、外へ走っていきました。これは困った! 博士も慌てて後を追います。
ロボットは高架橋へ来ると、線路めがけて飛び込みました。
「人身事故だ!」
人々が苛々と電車の復旧を待つ間、博士は路上からロボットの部品を拾い集め、すっかり元通りに直してしまいました。しかしロボットはうんともすんとも言いません。「電界」だけはどこかへ逃げてしまったようです。
博士はまた「電界」をもらおうと思いました。今日は平日・月曜日。女学生の他に通勤途中のサラリーマンが乗っています。できることなら有能な男性から電流をもらいたいものだ。博士はスーツ姿の男たちの傍へロボットを持っていきました。
スイッチを入れるとビリビリビリ、ロボットの身体を電流が通ります。目がぱっちりと開きました。
「クソジジイ」
低い声で、ロボットは言いました。
「俺様ヲ、散々、コキ使イヤガッテ!」
ロボットは片腕で軽々と博士を持ち上げると、ホームの端へ向かっていきます。復旧した電車が大きなクラクションを鳴らしながら近づいてきます。
博士が最期に耳にした言葉は、
「俺ニハ、時間ガ、ナインダ! 他人ノ事ニ、構ッテ、イラレルカ!」