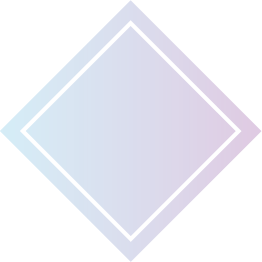レニーは死よりも深刻な病気に悩まされ続けていたし、これから先も永遠に続くと思っていた。
十七歳。噛み過ぎて味のなくなったバブルガムの爆ぜる年。とろみを帯びたバイオレットジュースの、マグマのような炭酸が爆ぜる年。
くそったれのセブンティーン。
人々はずっと自分の跡をつけていて、いつも自分を見張っている。それがレニーには気に食わない。
西部開拓時代のガンマンみたいに道端に飛び出して正々堂々と勝負しろ。どんな賭けごとにも勝てる自信が彼にはある。ひとたび戦いが始まれば、偶然にも超絶美女が通りすがりに自分の雄姿を見届けてくれる強運も持ち合わせている。
本当言うと、勝負事よりもその後の展開に興味があって、大抵それは自分の腹の上でのけぞる超絶美女の超絶なおっぱいをもみしだくところで終わってしまう。先を想像するより、実際に手で試してみる。誰にも邪魔されない、陰鬱な昼下がりだ。
レニーは起き上がると、Tシャツを着て、ジーンズを履く。ブラックTシャツの正面には火炎瓶の作り方がイラスト入りでプリントされていて、実用性のあるところが中々気に入っている。ジーンズは切り裂いたダメージが第三・第四の目のようにパックリ開き、合わせて第十六の目まで用意されていて、いつでもどこでも脱げるようにベルトの穴は緩めてある。
Tシャツの上からだぶだぶしたパーカーを羽織ると、大きなフードがまるで世界から自分の身を守る甲冑のように感じられ、護身用のスタンガンと自殺用のモデルガンを握りしめる手に力がこもる。
金があれば何でも買える。と、いうのは幻想である。と、いうことこそが幻想で、色褪せたポンコツ車の窓ガラスを拭いている乞食も自分と同じく真理を知ってる。それから裏通りに立ち尽くす売女も。
彼らはどこか自分と似ている、レニーは思う。彼ら以外にも「自分」と似ている人間は、世の中にたくさんいて、例えばマイケル、例えばケネディ、例えばヒトラー。最近になって彼らの苦悩が、手に取るように分かりはじめている。
頭の中では重低音のロックが響いて、歌詞は昔別れた女から電話を受け取る男の話。男は今でもその女を愛している。隣室には新しい彼女がいて、だから彼らの会話は深夜、ひそひそと交わされる。ああ、ハニー会いたいよ。
この男となら、読み解くのに二万年かかる複雑怪奇な自分の心を、語ってもいいような気がしている。
レニーにも、長い長い十七年の歴史の中で生き別れになった女がいる。過去にたった一人だけ。夢の中で確かに長い口づけを交わした。愛していると囁いて、朝日が昇るまで抱きしめていた。
その女にもう一度会いたい。抱き寄せて、腰まで届く長い髪を梳かしたい。心の底から、それさえ実現できれば死んでしまってもいいと思っている。今すぐにでも。
数ヶ月後、夢の少女を奇跡のようにレニーは見かける。平行に続く道路の端と端で、一瞬のうちに傍を横切る。
彼女はダサい灰色のワンピースを着ていて、長い髪を規則正しく左右で縛りつけている。
レニーはハッとして立ち止まり、通りを横切って彼女の元へ駆けつける。耳元で干からびたミミズのように丸まっている輪ゴムを外し、長い髪をかきあげる。口づけを交わすが、彼女の歯には昔にはなかった頑丈なブリッジが施されていて、檻のように舌を阻む。
唇からも薬用リップクリームの、心の萎えるにおいがするが、それも二人がベッドの上で抱き合うまでの話だ。彼女の胸で、きっと俺は泣くだろう。心の底から。生まれて初めて、自分以外のことで涙を流すに違いない。
そう思いながら、レニーは道行く彼女を見送る。さようなら運命の人。愛しい女。俺たちは不運な星の元に生まれてしまい、セブンティーンは死ぬまで続く呪いのようだ。
さようなら。ヒアアフターでまた会おう。この街ではないどこかでなら、もしかして上手く行くかも知れない……。
けれども、運命の人は、最後までレニーに気づかない。なぜなら彼女もくそったれのセブンティーン。
余命宣告された病人のように虚ろな瞳で、地面のタイルの色の変化を観察するのに夢中だからだ。