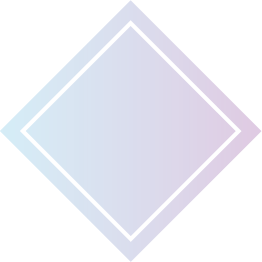ウィリアムへ
君がこの手紙を読んでいるってことは、どうやら僕の伝言は上手く君のもとへ届いたみたいだね。
はじめに断わっておくけど、僕が最後に手紙を書いたのは六歳のとき、パパの誕生日にバースデーカードを贈ったきりだ。
手紙らしい手紙なんて書いたことがない。ここまで読み返して、早速スペルの違いを五か所ほど見つけたよ。
君にとっちゃこの手紙は手の込んだ暗号文みたいに見えるんじゃないかと思う。もしくはたちの悪いいたずらか。
どうか君が最後まで投げださずに読み終えてくれることを願うばかりだ。
早速、本題に入ろう。君が気になっているであろう、ブルーフェアリーについてだ。
直接、僕から君に渡したかったのだけれど、どうやら時間がないみたいだ。
先日、黒いフロックコートを羽織った例の男がうちへ来た。そう、君がいっていたジャックという男。僕はすぐに彼の正体に気が付いたよ。あいつは私立探偵だ。ブルーフェアリーのことを調べに来たんだ。前にも話した通り、僕のネットワークは二重にも三重にも入り組んでいる。証拠がなければ警察もうかつには踏み込めない。そこで法に縛られない民間人の登場ってわけさ。
ジャック、鋭い男だ。
彼に比べれば警察なんて歯の折れたナイフ、穴のあいた虫取り網さ。
探偵はいずれ僕のネットワークを隅から隅まで日のもとにさらすだろうと思う。この業界に大混乱をまき起こすかもしれない。そうなってからじゃ遅すぎる。僕は一足先に退場することにしよう。
ウィリアム、分かっているね。この手紙は警告でもあるんだ。黒いフロックコートには十分に用心した方がいい。僕がいなくなってから三日もしないうちに、矛先は君へと変わるぞ。気をつけろ。
さて、そろそろ僕のかなくぎ文字にも飽き飽きしたころだろうと思う。最後に、肝心のブルーフェアリーについて記しておく。僕の最後のブルーフェアリー、まるごと彼女に託しておいた。そう、僕と君の共通の友人でもあり、緑色の瞳をしている彼女だ。頃合いを見計らって、取りに行ってくれ。
もちろん、彼女はブルーフェアリーのことを一切知らない。くれぐれも迷惑はかけないようにお願いするよ。僕のブルーフェアリーもこれで品切れだ。大切に使ってほしい。代金は、次に会ったときでいい。
なにか運命のようなものが僕らの間に作用したら、また会うこともあるだろう。
ただ、ブタ箱の中でだけは勘弁願いたいところだがね。