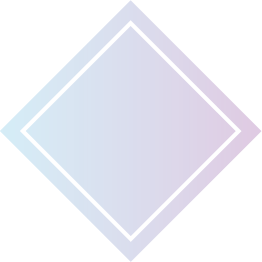人気モデルのreinaが死んだ。都内にある一人暮らしのマンションで。お酒と睡眠薬をたくさん飲んで。
朝、「訃報」と名のついたニュースが速報で流れてきて、あたしはシリアルと牛乳を飲み込むタイミングを逃してしまった。
スマートホンの画面をスクロールしてみる。ネット上で繋がっている、あの子もその子もreinaのことを話題にしている。だからあたしは、今日はどんなSNSにも記事を書かないと心に決めた。
実はreinaのこと、好きじゃなかった。
パグ犬みたいに下ぶくれた顔が生理的に受け入れられなかった。バラエテイのコメントが下手くそなところもイライラしたし、雑誌に載ってた私服が銀紙っぽいところとかマジで最悪だった。
好きじゃない人間が生きてようが死んでようがどうでもいい。ただ、スマートホンに表示される見たくもない情報がウザい。学校でその話に乗っからなきゃいけない空気も面倒くさいし、いかにもショックを受けたような顔をしなくちゃいけない同調圧力も大嫌い。
テンションだだ下がりのあたしに与えられた唯一の休息は、登校中の今しかなかった。「reinaやばくね?」って友達から届いたメッセージを見なかったことにして、好きなアーティストの曲を流しながらいつもとは違う道をなんとなく選んで足を止めた。衝撃的な記憶がよみがえった。
ここ……、あすかちゃんが死んだところだ。
中古車を販売するのお店のとなり、単線線路の上にかかった小さな石橋。その橋に張り巡らされた落下防止の緑のフェンス。そのフェンスの外側にかかった役ただずの赤い欄干。
その欄干からあすかちゃんは落っこちた。五メートル下の線路に叩きつけられ、通りかかった電車に轢かれて死んだ。
小学四年生のころのことだ。
どうして今まで忘れていたんだろう。
あすかちゃんが人生最後に話した相手は、(たぶん)このあたしなのに。
あすかちゃんちは複雑で、お母さんはあすかちゃんが幼稚園生の頃に離婚していて、そのあとで新しいお父さんが三人くらいできて、でも今は彼氏がいるらしくて、その彼氏はあすかちゃんのことが嫌いだから、お母さんはあすかちゃんを放置して彼氏と会っているとかなんとか。
あすかちゃんには年の離れたお姉さんがいるらしいけど、そのお姉さんも中学を卒業したあとで彼氏を作って家を出ていってしまったとかなんとか。
マセガキのあたしたちが聞きつけた噂は、だいたい間違っていなかったと思う。「こんな家出ていってやる!」って去り際にお姉さんの吐いたセリフが、すっかりあすかちゃんの口癖になっていたから。
「こんな家出ていってやる!」
そんなあすかちゃんはクラスでもかなり浮いていた。その浮き具合たるやイジメのターゲットにすらなれない悲惨さで、あたしたちと生きる環境が違いすぎる彼女は、触れた瞬間呪いを振りまく不気味な神様みたいだった。
「触らぬ神に祟りなし」と、あたしたちは眺めるだけにしておいた。猿みたいな顔を引きつらせ、上目遣いにあたしたちを、学校を、母親を、世間を、世界を、宇宙を、睨みつける汚い女の子の姿を、遠巻きに。
あたしとあすかちゃんの接点は、最後の日まで何もなかった。
コンパスで描いた円の中心にあすかちゃんがいて、あたしやクラスメイトたちは同じ分の半径を取った周縁の線に過ぎなかった。あすかちゃんも、あすかちゃんの母親も、そのお姉さんも、あすかちゃんの母親の彼氏も、あたしたちから見れば遠い国のおとぎ話。物語の登場人物みたいに、薄っぺらな存在でしかなかったのだ。
だから、あすかちゃんに話しかけられたときはびっくりした。クラス中から気味悪がられている不幸の神様が、真っ赤な欄干の上に仁王立ちしているなんて想像もしていなかったから。
「おいっ!」
「わっ、あすかちゃん!」
あたしの言葉にあすかちゃんは驚いたようだった。
ポカンと口を開けたまま、
「……あたしの名前、知ってたんだ」
ごくっ、と唾を飲み込む音が聞こえた。
「知ってるよ。クラスメイトじゃん」
慌てて笑顔を繕いながら、ほんとは息も絶え絶えだった。今しがた別れた友達の笑顔が恋しかった。早く帰りたかったけれど、このままあすかちゃんを放置しておいたら「あたしは最低な人間です」と自分自身に宣言しているように思えて、それだけは絶対に避けたいあたしは仕方なく会話を続けた。
「あの……あすかちゃん、そんなところにいたら危ないよ。下、線路じゃん。落ちたら死ぬよ」
「良いんだ」
「えっ?」
「こんな家、出ていってやるんだから!」
出た、名台詞。
誰も何も聞いてないのに、つい口走っちゃう心の叫び。
「今日こそこんな家出て行ってやるんだ。そして二度と帰らない」
フェンスを外側から揺らしながら、あすかちゃんはきひひっ、と甲高い声で笑った。
そのとき、小刻みに石橋が揺れた。ガタガタガタガタと不穏な音を響かせながら目下五メートルの線路の上を電車が走り抜けた。
橋が揺れるのとほぼ同時にあすかちゃんは片手を離して電車へ身を投げ出した。フェンスを掴んだ手を軸にして、痩せっぽちの身体が風に吹かれた葉っぱみたいに右に左にくるくる回る。
きゃーっ、とあたしは悲鳴をあげた。
あすかちゃんはケラケラ笑いながら、宙に揺れていた手をフェンスに掛け直した。
「あと十回やって、成功したらあの家を出て行くんだ」
「あすかちゃん! マジで死ぬよ!」
「関係ねーよ。それよりここで見といてくれよ。十回。証人が必要なんだよ」
「や、やだよ! あすかちゃん、やめてよ!」
「やめてほしいなら、来いよ。ここまで来て、止めろよ、あたしを……」
「やだよ! 死んじゃうもん! やだ!」
「意気地なし! このくらい、簡単じゃないか!」
あすかちゃんはフェンスを左右に揺らしまくった。フェンスが破れたら、十本の指が外れたら、足がつるっと滑ったら……考えるだけで足がすくんだ。自分の命で遊んでしまえる、あすかちゃんにゾッとした。
ゾッとしながら、冷めた頭であたしは思った。
かわいそう。
「意気地なし! お前も、クラスのやつらも、群れるしか能がない意気地なしだ!」
かわいそうだ。
この子は、かわいそうな子なんだ。
小四ながら、あたしは、はっきりと感じたんだ。
人間には、見えない「クラスわけ」が存在するんだと。
……思っていることが顔に出やすいって今でもよく言われる。
お母さんとか、彼氏とか、友達とかに。
そのときのあすかちゃんもあたしの顔を見た。すぐさま怒りに顔を赤らめて、
「……もういい、帰れ。帰れよ。あたしは行く。こんな家出て行ってやるんだ。今日限りで家とも、学校とも、お前らともおさらばだ。本当に、こんな家、出てってやるんだから!」
興奮した猿みたいに歯を剥いてフェンスを鳴らしまくった。ガシャガシャ、ガシャガシャ。
大きな音を立てて左右に激しく揺れるフェンスは、しかし、絶対に破れなかった。
お腹の底から味わったことのない恐怖が込み上げ、猛ダッシュであたしは逃げた。
頭の中では、呪文のように一つの言葉が繰り返されていた。
あすかちゃんじゃなくて良かった。
あすかちゃんじゃなくて良かった。
あすかちゃんじゃなくて良かった!
そして、あすかちゃんは死んだ。
大人たちは、事故で死んだと言っていた。欄干に登って遊んでいるうちに、誤って転落したのだと。
あすかちゃんが死んで、彼女の存在を完璧に忘れてしまうまで、あたしたちは噂した。
あすかちゃんは事故死した。
でも、本当に事故だったのかな?
かわいそうなあすかちゃんは、そうやって、家を出て行くしかなかったんじゃないのかな?
スマートホンがぶるっと震えて、画面を見ると登録してあるニュースサイトの通知が出ていた。その通知には「reinaの死は自殺とみて警察は捜査を進めている」と書いてあった。
自殺。薬の大量服薬で自殺。
確かに、そうかも知れない。芸能界、闇深そうだし。ネットでreinaの変な噂、たくさん見ちゃったし。reina、テレビで見るたび痩せていってる感じがしたし。
頭の中で四回くらい同じ感想を繰り返して、あたしは携帯を鞄にしまう。
そして石橋の端から背伸びして、乾いた色のフェンスを握る。ガタガタガタガタガタ。遠くから響いてくる振動。
ほんとのところは、きっと誰にも分からない。
今、あたしが思っているのは、自殺と事故の境界線は思っているほど揺るぎないものではなくて、むしろ死んだ人にしか引けないんじゃないかってこと。
かつてひとりの女の子が落ちていった暗い溝――その境界線は足の下で、電車の走行音とともに今も激しく揺れている気がした。