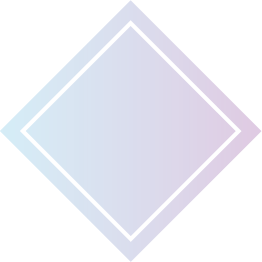動物園の扉が開いていたので、中へ入ってみることにした。暑い夏の夜のことだった。扉というより檻に近い引き戸は滑らかにスライドした。影のように中へ入って、後ろ手にガシャリと閉めた。
園の中はしん、と静まり返って、酸素の割合がどことなく高い。誰の声も聞こえない。青空の代わりに真っ黒な夜空が頭上を覆っている。全てのものが暗転し、ぼくだけが昼間のシャツに昼間のジーンズ、携帯電話のストラップをぶらぶらさせながら、昼の姿のままでいる。
売店や土産物屋にはシャッターが閉められていた。外側から南京錠がかけてあって、表面にはアカやピンク、ミドリのペンキでライオンの絵やウサギの絵が描かれている。動物たちの頭上で真っ赤な太陽と真っ青な地球がべたべたに塗ってある。
入ってすぐ、道は上り坂になっていた。坂の途中、道が二股に分かれている場所があり、中央に矢印型の立て看板が見える。
右:アフリカに生息する動物の檻。
左:アジアに生息する動物の檻。
手はじめに、アフリカの動物たちに逢いに行くことにした。
フラミンゴ
アフリカ園はあちこちに溝や堀があり、穴も空いていた。サバンナの動物は体が大きかったり性格が凶暴だったりするので、我々と動物を隔てる敷居がくっきりしているのだ。凹凸の激しい地形が一様に月の光を浴びて黒い影を落としている。ライオンの住処は人を遠ざけるため深い谷底にあった。ぼくは観賞用の手すりに身をもたせて、目下を覗き込んだ。
アフリカ園の三分の一ほどの敷地面積を使った広野に、ライオンは一匹もいなかった。ライオンバスが通過するアスファルトの上にも、小高い丘の上にも、架橋かきょうの下にも、動物らしきものの影は見当たらなかった。いつもなら弛たるんだ脂肪と乱れたタテガミをゆらゆらさせて雄ライオンが何匹かいるはずだった。そしてどれがどれだか見分けのつかない雌ライオンも、雄の数の三倍くらいいたはずだ。
何もない。
それどころか、周りの檻にはジラフもゼブラもチーターもエレファントもペリカンもない。何もない。そうかアフリカの動物たちは、夜は飼育舎に入れられているのだ、と気がついた。園の片隅では、美味しそうな果実のように身を寄せ合って、フラミンゴが密やかな眠りについていた。
フクロウ
ぼくはアフリカ園から猛禽類の住まう檻へ向かうことにした。この辺りも急勾配が続いており、坂の途中に傾いた木箱がいくつかある。フクロウが一羽ずつ整頓されているようだ。フクロウたちはぱっちり目を開けて大きな瞳でこちらを見ていた。
昔、何かで読んだことがある。フクロウの好奇心は強く、興味のあるものを見かけると、睡眠時でも目を覚まして対象を観察するのだそうだ。昼間見かけるはずの人間が、こうして闇の中に佇む姿が興味深かったのだろうか。一つ、灰色い身体の伸縮自在なヤツが伸びあがったまま、ぼくがいなくなるまで元に戻ろうとはしなかった。無数の丸い目に追い立てられるように、ぼくは群れの外へ出た。
やはり行くならアジアがいい。パンダやオランウータンや、トラやシカ。
きっと居心地がいいだろう。
ヘンな動物
アジア園に向かう坂の途中でヘンな動物に出くわした。そいつはサルのようにも見えたが、どことなくサルとは違っていた。ピンポン玉の大きな瞳、鼻が豚のように上に持ちあがって、細い首筋はネックレスのようなアカとミドリの羽毛に覆われている。向こうの道を二足歩行でやってくる。放し飼いされている動物だけに害はないのだろう。ぼくはその動物に向かって挨拶をした。どことなく親近感がわいた。
そいつは首をぐんと持ち上げ、ぼくのことを凝視したまますぐ横を通り過ぎた。
バク
噴水には放し飼いにされたバクがいた。アジア園に住まう他の動物は飼育舎で眠っているらしい。ぼくはアジア園の檻を見て回ったが、それらを除いて動物は一匹もいなかった。
バクたちは水を浴びたり飲んだりしていたが、やがて列をなしてぞろぞろとどこかへ向かって行った。鉄筋コンクリートの打ちつけられた四角い小部屋があり、壁のパネルには「スイミングルーム」と書いてある。バクたちを刺激しないように、十分な距離をとってぼくも部屋に入った。
スイミングというからにはプールでもあるのかと思ったが、一階のホールは何もなかった。部屋の中は明るく、長いスロープが上へと続いていた。バクを見失ってしまったが、天井から動物の鳴き声を頼りにスロープをのぼって行く。途中でコロコロしたものをたくさん踏んづけたが、確認しなくともバクの糞だと分かった。
スロープは何十も螺旋を描いて、今まで歩いてきた坂道よりもうんと長く続いていた。壁にはめ込まれた細長い窓ガラスに夜空が映っていた。外を見下ろすと、動物園の建物は豆粒のように小さく、全体が端から端まで見渡せる。
カンガルー
アジア園の先はコアラやカンガルーの住むオーストラリア園になっている。ノミのように小さなあれはカンガルーだろうか。ざっと見積もって五十匹以上はいる。カンガルーたちはぴょんぴょん飛び跳ねながら坂道を下ってきた。そしてアジア園の噴水の周りを輪を囲んで踊り始めた。何かの儀式のようでもあったが、ただ重力に逆らって噴き出す水に興奮しているだけかも知れなかった。
園の外は背の低いマンションや民家の続く住宅地になっている。こんな真夜中に電気をつけている家も少なく、強く光を放っているのは、二十四時間営業のコンビニエンスストアだけだ。いつもなら煩わしいと感じる白い発光も、どこか恋しく、柔らかい。
スロープの終いにはアルミ製の大きなドアがあった。金庫室の扉のように頑丈で、防音措置も施されているようだったが、その中から微かに動物の声が聞こえてきた。ネコのようなもの、トリのようなもの、そのどれにも当てはまらない得体の知れない遠吠えも響いて、ぼくはわくわくしながら扉を開けた。
動物たち
重い鉄音を立てて扉が開くと、煌々とした光に照らされた。満月だ。目と鼻の先にある。
ドアの周辺にはランが鬱蒼と生い茂っていて、人の髪の毛に似た葉がアーチのように視界の隅に垂れ下がった。奥へ進むのに草をかき分けなければならなかった。
天蓋は星々に覆われていたが、部屋の彼方は完全に陽が落ちていないらしく、オレンジ色の夕焼けがぼやぼやと地平線を滲ませていた。その間を塔のようなバオバブの樹が何本も聳え、黄昏の中、複雑なシルエットを描き出していた。部屋にはオアシスのような水のたまりが左右に二つできていて、たくさんの渡り鳥たちが水遊びをしていた。その傍らではゾウやキリンが各々群れを作って水を飲んでいる。部屋の手前にある大きな岩場で雄ライオンが雌たちに囲まれてうっとりと寝そべっており、黄金の瞳を閉じたり開いたりさせていた。数羽のフラミンゴがつかず離れずして空を横切った。
夕暮れの熱帯雨林、空に浮かんだ満月、水のたまり、動物たち。大地は無限に続いている。
ぼくはこの光景をどこかで見たような気がした。少し考えているうちに、それは記憶にも遠いどこかの壁に飾られていたシルクスクリーンの絵画だということに気がついた。ビビッドな色彩で、こんな風に世界の果てで戯れている動物たちが描かれていた。生まれてから見てきたものの中で間違いなく、一番美しい絵画だった。
アジア園に向かう途中に出会ったヘンな動物たちもいた。
彼らは左側にあるオアシスに寄り集まっていた。数にして十匹程度、人間の子供くらいの大きさで、みんな首にきれいな羽飾りをつけている。ぼくはライオンの脇をすり抜け、ヘンな動物たちの方へ歩いて行った。ヘンな動物の何人かはチラリとこちらを振り向いたが、何事もなかったかのようにまた視線を元に戻した。
群れの中で一番大きなヤツが他の連中に講釈を垂れていた。身振り手振りを交えて、我々の祖先は地球という星に暮らしていたのだが、食物連鎖にウンザリしてね。同志を連れてこの星へ逃げて来たんだ、と説明していた。
ヘンな動物が頭上を指さすと今まで満月だと思っていた明るい星が、実は地球だったことに気がついた。赤黒く変色しているだけで、世界地図で目にした模様そのものだ。ヘンな動物は天を指さしながら、子どもたちに星の名前を教え始めた。地球を除いて、どれも耳にしたことのない名前だった。
ぼくはそこにいる動物たちを撫でたり触ったりした。頭に触れるとヘンな動物はあからさまに嫌がる素振りを見せたが、他の動物たちは怒るどころか逃げも隠れもしない。本能を内側に隠した、思慮深い眼差し。ぼくを見つめたまま、ライオンもサイもシマウマも、黙ってされるがままにしていた。その知性溢れる瞳の奥に、憐憫がちらりとかすめたような気がして、ギョッとした。思わず手を離した。気の毒そうに眼を伏せると、ライオンは地面に頭をおろして無声で唸った。諦観。彼らはもう「動物たち」でなくなってしまっていた。一人一人に名前があって、意思があって、きっと主義や思想もあるに違いない。
ぼくたちだけの特権であったものが、全てのものに与えられている。それ以上に、ぼくらに成し得なかったことを、彼らは達成している。ここでは全ての生きものが平等だ、あの地平線のように。恐ろしい。
扉を開けて、転がるようにスロープを駆け降りた。部屋の外へ出た。噴水に飽きてしまったのかカンガルーたちは見る影もなく、動物園の外に出るまで、どんな動物にも出くわさなかった。
ぼく
コンビニまで走った。けばけばしい人工灯を全身に浴びると、混乱の糸が徐々にほぐれてきた。落ちついた。「スイミングルーム」で見たことは、全部夢だと思うようになった。そうだ、ぼくは幻を見ていたんだ。あれは夢、夢に違いない。たぶん……。
すぐさま引き返してみたものの、動物園の扉は鎖が何重にも巻きついて、完璧に閉ざされてしまったあとだった。扉を施錠していないことに誰かが気づいたのだろう。誰にも見つからずに不祥事が揉み消せたと、今頃は胸をなでおろしているかも知れない。
現に、ぼくが真夜中の動物園へ忍び込んだという証拠はないのだ。動物たちの記憶の底を除いては。
動物たち。彼らはきっとぼくのことをいつまでも覚えているだろう、記憶の底の、底の方に。彼らはきっと忘れない。真夜中の闖入者を、永遠に忘れない。
壮大な歴史の中で、ぼくだけが昼間の姿のまま、まるで雨の日に照りつける太陽みたいにイレギュラーな存在だったわけだから。