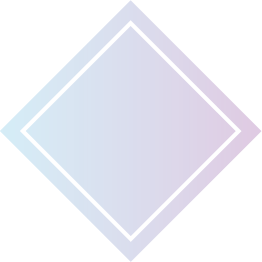一、監督
駄目だ! 取り返しのつかない失敗をした! こりゃァ、何をしても駄作だよ! こんなもん、人に観せる価値もない!
監督がメガホンを女優の尻にぶつけたとき、辺りを取り巻いていた108名の羽の生えたスタッフたちは一斉に溜息をついた。
……もちろん心の中で、だ。
一体、何回目だろう。監督の癇癪も。もしかすると我々スタッフの人数より多いかも知れない、と皆して思った。
布張りの椅子から飛び降りると、監督は赤ん坊のように贅肉のついた手を挙げて、第三愛人兼美人秘書を呼びとめる。ごにょごにょと何か耳打ちし、耳打ちついでにこっそりと(本人はあくまで〝こっそり〟と思っている)美人秘書の頬にキスをすると、そのまま部屋を出て行ってしまった。
ばたーん! と扉の閉まる音は、下界に住む女優の耳にも届いただろう。裸身を映し出す鏡の前で、女優は不思議そうに首をひねって天井を見つめた。スタッフのうちの一人が慌てて拍子木を鳴らすと、下界の女優は不思議そうな顔のまま、銅像のように固まった。
件の監督は名匠である父から受け継いだ独特の美的センスで素晴らしく壮麗な映像を取ることで有名だったが、いかんせん、仕事中少しでも気に入らないところがあると部屋から飛び出してしまうところが玉に瑕だった。聞けばかつての名匠も、人遣い――否、スタッフ遣いの荒いことで有名だったそうだから、映画作りに関しては父性遺伝のすべてを受け継いでしまったらしい。
また、父子ともに飽き症であり、別のジャンルの作品を同時並行して撮ってしまうところもそっくりだった(つまり、典型的な天才型の家系なのだ)。
美人秘書は108名のスタッフを集めて、監督はこれから日本で起こる大震災のドキュメンタリーを撮るつもりであることを告げた。舞台セットは既に出来上がっていて、カチンコを鳴らせばすぐにでもクランクインできるという。それを聞いて、スタッフたちは再び苦悩の溜息をついた。
父性遺伝子の他、スタッフたちの悩みの種になっているのは、とにかく壮大なテーマを掲げて映画を作りたがる監督の凝り性だった。それは業界内でも懸念の対象になっていて、たまたま監督が白羽の矢を立てたのがアジアの小さな島国であったから良かったものの、以前のように地域や大陸を競わせて戦争映画を撮ろうものなら今度こそ本当に地球が滅びてしまうのではないかと思われた……それでもあの監督のことだから、例え世界が滅んだとしても「創世」をテーマに何かしらの作品を作り上げてしまうのだろうが。
今回の舞台セットだって、スポンサーに無理を言って壮大なエネルギーを捻出してもらっていた。テーマの方も個人レベルには壮大で、タイトルもまさしく「女の一生」。日本映画の巨匠の作品からもろに影響を受けていると思われる。
スタッフたちは鏡の前で裸身をさらしたまま停止している女優・芙美子を顧みた。
「女の一生」は三分の二ほど撮り終えたばかりだった。この映画の核ともなる名シーン、四十歳を迎えた芙美子が鏡の前で自身の疲れた裸体を映し溜息を尽く、というところで監督が怒り心頭に発したのは、芙美子の乳首が黒過ぎるくらいに黒いというそれだけの理由だ。
美術係のスタッフが現代技術で乳首の色を修正できると進言したが、監督はどうしても「天然モノ」にこだわった。CGを使った画像加工は観客の目に不自然に映ってしまう、と言うのだ。
女優の演技を一秒たりとも見逃さずにいた監督は、芙美子の乳首の黒さは相手の男優・向田佐吉にあると断言した。佐吉のやつが変態性欲を丸出しにして芙美子の乳首を噛み過ぎるからいけないのだと言って譲らない。
佐吉を馘にしてスタッフのうちの誰かが代役を務めろ。俺が求めるとおりに演技しろ……との指示がでています、と美人秘書が囁くように説明するのをスタッフ達はげんなり顔で聞いていた。四十年にもわたって撮り続けてきた大作を、乳首の黒点一つで白紙に戻してしまう監督の大胆さには呆れる他ない。副監督のスタッフを中心に据えて、108名が円陣を組んで話し合った結果、ただ若いからという理由で最年少の小道具Dが抜擢された。
先輩たちが相手ではスタッフDも嫌とは言えない。御意のしるしに背中の羽をぱたぱたさせると、周りのスタッフも同情の意味を込めて背中の羽をぱたぱたさせた。
そして、すべての照明が消える。
二、男優・佐吉
しばしの幕間を置いて世界の明かりが灯るころ、Dは三陸地方の山奥にいた。
フィルムをかなり巻き戻したなと思い腕の時計を見たところ、時計盤の中心に19270801とデジタル数字が表示されていた。つまり1927年08月01日。本日の天気は晴れのち雨。夕方から土砂降りの、豪雨。
シナリオでは今日の朝、芙美子の人生に向田佐吉が登場することになっている。
具体的な時間で言えば午前九時四十三分、佐吉はこの山道を通って、芙美子の家へ父親から預かった中元の品を届けに行く……というのも佐吉の父親は、かつて芙美子の家に丁稚として勤めた恩があるのだった。
主従を超えた二人の男親は友情のしるしに互いの子供を許嫁にする約束を取り決めていた。十六歳の男女の慣れ初めは互いの両親の合意による意図的なものだった。時代も時代ながら、その後のフィルムを見る限り、芙美子と佐吉の仲は悪くない。映画の題材になるほどの様々な憂き目を見てきた芙美子だったが、伴侶にだけは恵まれていたと言えよう。
すべてが微笑ましい計画の下進行してゆく運命を変えることはDにとって心苦しい決断だったが、元来の仕事熱心な性格が躊躇する彼の背中を押した。
午前九時四十三分、佐吉の姿を確認するや否やDはワッと茂みの中から躍り出て、手にしたナイフで佐吉の身体を切りつけた。その頃から文学青年の兆しがあった佐吉は、町の貸本屋で借用した大衆雑誌に見入っていた。
だから最期まで彼は気付かなかった、抵抗の術なく一閃が、彼の痩せこけた若い胸板を両断したなど。
――佐吉の活字中毒は晩年まで続き、Dは映画を撮っている間、彼から様々な小説を教わった。この時期に彼が傾倒していた江戸川乱歩や芥川龍之介、コナン・ドイルやエドガー・アラン・ポーなどの奇妙奇天烈な話はどれも面白く、彼が三十代の苦行の中でしがみつくように読んでいたプロレタリア文学も、四十代で祈るように熟読した太宰治も、佐吉の人生を知っているだけにじんじんと心に響くようだった。
けれどもこの先出会うべき本は、今この瞬間、佐吉の人生とは無関係になってしまった。数年後に感銘を受けるはずのあの本も、戦時のまっただ中やっと手に入れたあの本も、転職のきっかけとなったあの本も、すべて佐吉と関わる術を失った。運命のレールが切り替わる「ゴトリ」という音と共に、別れを惜しむ本たちの嗚咽がDの耳に届いた。
この世界の人間でない自分は運命の干渉を受けるはずないのだが、佐吉の身の上を思うとゾッとした。出会うべきものに出会えない哀しさは、当の本人がその哀しさに気づかぬところだとDは思った。
もしかしたら、自分もまた知覚できない次元からすると哀しい生物であるのかも知れない。
三、スタッフD
運命は、チューブから無限に絞り出される練り歯磨きのようだ。
次元外の人間に抹殺されてしまった場合、死した人間の形に運命の生地に穴が空く。そのまま放置しておくと世界の均衡が破綻してしまうので、すぐさま別の生地がなだれ込み、いなくなった佐吉の溝を埋めようとする。様々な人間が佐吉の身代わりの行動を取るのだ。
ただし、マイナス1となった世界にDのようなプラス1の人間が紛れ込んでいると、運命は物理的に部外者を身代わりに立てる。
その性質を利用してDは佐吉になり済ますと、持っていた中元の小包を携え、芙美子の家に向かった。
先程まで佐吉が読んでいた雑誌は「新青年」だった。初出の乱歩小説にひどく感動しているうちに、Dは自分を向田佐吉だと思うようになってきた。芙美子に出会ったあとも、月日を重ねる度に強さを増してDの意識を侵食し始めた。
運命の干渉を受けるはずのないDが佐吉に変容する。それはあり得ないことだった。
敢えて理由を求めるとすれば、共有した様々な書物が彼の人格を向田佐吉に近づけてしまったと言うほかない。撮影フィルムを通して体感した昭和時代と、彼の思想の一端を担った佐吉経由の書物が、年若い故に脆弱なDの自己認識を崩壊し、錯覚させたのだ。
役に入り込み過ぎて劇中人物から抜け出せなくなった役者のように、Dと佐吉の意識は渾然一体となって境界線を失った。今やDを冷静に立ち返らせるのは、外部スタッフが軌道修正のために流す腕時計の電流だけだった。
そうだ、俺はDだ。佐吉ではない、映画スタッフのDだ……。
数年ごとにDは腕時計の電流によって本来の自分に戻った。両父親の共通の友人が仲人を果たして無事に芙美子と結ばれたときなど、焼痕がつくほど強くDの腕に電流を流さなければ幸福感に包まれて自我を失っていただろう。
けれども次第にDの身体は電気刺激に耐性がつき、若い二人に襲いかかる嘘のような苦難の連続をへとへとになって乗り越えているうちに、意識は完全に向田佐吉に覆い尽くされてしまった。初めのうち感じていた「俺の同僚たちは今どんな思いで映画を撮っているのだろう」などというメタフィクション的な感情はとうに消えうせ、ただ目の前にいる一人の女を愛することだけに全力を注ぐようになった。
DはDであることを、佐吉が死ぬまで思い出せない。
それでも電気ショックによる強いトラウマは残っていて、愛を交わす際、向田佐吉は絶対に妻の美しい乳首に触れようとはしなかった。
四、女優・芙美子
本日は雨にもかかわらず、夫のためにご会葬賜りありがとうございます。
私は、故人・向田佐吉の妻でございます。遺族、親戚を代表しまして一言ごあいさつ申し上げます。
夫は、九月六日、肝硬変のため永眠いたしました。享年七十三歳でした。生前お酒が大好きで飲酒量も多く、量を減らせないのならばせめて良酒を飲んで欲しいとお願いしていましたが、若いころ貧乏をしたためか、舌に沁みついた安酒の味を変えることはありませんでした。
闘病に苦しむ夫の姿を見るのは腸を断たれるほど辛いものでしたが、最晩年はお薬で痛みも薄まり、最期は自宅の布団の上で眠るように逝きました。
夫と二人三脚で生きた五十年は人並みながら良いことも悪いこともありました。よく人から「苦労なさったでしょう」と聞かれるのですが、そんなことはありません。二人で力を合わせる生活は、お金は不足しておりましたが充実したものでした。
これからの人生、主人との思い出を胸に残された家族で支え合い生きていきたいと思います。
故人の生前と同様に、皆さまのお力添えをいただければ幸いに存じます。
本日は最後までお見送りいただき、ありがとうございました。