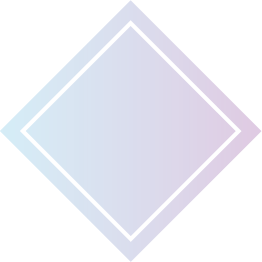■わずか一日でその国は滅んだ。
■私がこの話を聞いたのは、数十日ばかり後のことで、語り部を務めた当時の少年は花びらの抜け落ちた老爺と化していた。夏草の生い茂った小高い丘の上に少年老爺の住まいがあった。同時に、そこはかつての戦場でもあった。
老爺の近くに同胞の気配はない。誰も彼もがやられたのだ。老いも若きも、背の高いのも低いのも皆一様に、あの空に。
■積み重なった骸の上に立った彼女たちはまるでヴァルキューレの行軍のようであった。同胞たちの魂の宿った白い蜜を腹に収め、彼女たちは今にも飛び立とうとしていた。少年は隣家の少女の背に隠れていたので助かった。もっとも、体液をしぼりとられた少女の身体は今にも空へあおられそうになっていたので、少年は力を込めて少女の皮を大地につなぎ留めなければならなかったのだが。
彼女たちは再び舞い上がった。空の彼方へ小さくなって、それきり二度と姿を現すことはなかった。
■キスをされた一人の身体から血の気が失せ、みるみるうちに萎れていった。崩れ落ちたその人を見ると、体内にほとばしっていた生命の蜜がねこそぎ奪われており、あちこちに気味の悪い皺が固まって大きな筋を作っていた。ひたいに空いた小さな穴からは水滴にもならない生命の名残が、きらきらとした湿り気を残している。彼女たちは歌を歌いながら、ごちそうに飛びかかった。
■赤や黄、青や桃に色づいた羽は、まるで虹の中から生まれ出たようだった。彼女たちは踊るように羽ばたいて、しとやかに降りたつ。穏やかな風が脇をすり抜け、身体にまとった光の粉を方々へふりまいた。まるで、生きとし生けるもの全てに、祝福をささげているかのように。物珍しさと美しさで、地上のものは眩しそうに彼女たちを見上げた。彼女たちの一人が、背の高い同胞に身をかがめてキスをした。
■それは偶然が起こした、些細ないたずらにすぎない。強風が一陣吹いたため、身ごもった女の綿毛が空へ舞い上がっただけ。それがたまたま彼女たちの傍を通り過ぎて行っただけだ。けれども、彼女たちの注目を誘うには十分だった。彼女たちは目下を見下ろす。そこには生命の蜜をうちに秘めた、黄色いたんぽぽの群れが、鮮やかに咲き誇っていた。
■彼女たちがやってくる前の丘は美しく、黄金の花々が咲き乱れていた。たんぽぽたちは互いの顔を見合わせて言ったものだ。
「我々は美しい。なぜならば天の陽が、その身を模して我々をお造りになったからだ。我々は神の子。ここは楽園。神の庇護の元、王国は永遠に続くだろう。」と。