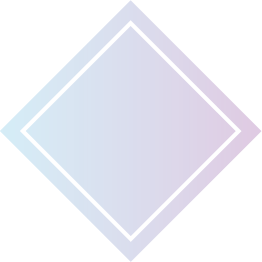麗らかな春の陽に誘われて少しばかりうたた寝をしていたものですから、兄様が席に着いても私は全く気がつかないでいたのでした。
ぱら、ぱら、とページを繰る音が聞こえ、目の前には兄様の不機嫌そうなお顔。眉間に皺を寄せて、私の絵本を読んでいます。
「ウンデナ」。それは、今は亡きアイルランドの作家が残した哀しい人魚の物語。お話の最後で、彼女は精神を病んでしまいます。海底の洞穴に閉じこもり、人魚は孤独のまま生涯を過ごすのです。
兄様は全てのページに軽く目を通すと、テーブルの上に投げ捨ててしまいました。フン。兄様が鼻で笑うと、足元に咲いたチューリップの花までもがそよそよと、共に笑っているかのよう。
「くだらない。こんなもののどこか面白いのか、僕には理解不能だよ。安っぽい涙を誘うだけの子供だましじゃないか」
君はもっと深い話を読むべきだ。精神に打撃を与えるような、真摯な物語を――兄様はロッキングチェアーにもたれかかると、小さく欠伸をしました。
「精神に打撃を与える本というのは、例えばどんなものがあるのかしら?」
私が尋ねたところで、兄様に分かるはずがありません。兄様が本を読んでいるところなど、私は一度として見たことがないのです。
お前には付き合い切れないよ、というように兄様はひらひらと手を泳がせました。その白い手がジャケットの胸元に伸び、兄様はパイプを取り出します。父様が愛用されている陶器製の白パイプ。父様の不在を良いことに書斎からくすねてきたのでしょう。兄様はパイプに火をつけると、ぷかりぷかり、父様の吸い残しをくゆらせます。あどけなさの残る兄様の口元に大きなパイプが不釣り合い。パイプのせいで益々兄様が幼く、可愛らしく見えてしまう事に当の本人は気づかない。
大人ぶってはいるけれど、兄様はまだまだ子供なのです。背丈も私と変わらないくらい小さいし、声もきりきりと高いまま。兄様が父様やお爺様と同じ、「男の人」だとは思えません。
むしろわたしに近い、少女のようなお姿なのです。
「それよりもどうだい、僕の箱庭は? 居心地が良いだろう?」
そう言われて、私はもう何百回と見渡した庭を、今一度眺めました。
庭はとても狭い。二歩も歩けば薔薇の生け垣にぶつかってしまいます。生け垣は二メートルほどの横幅を残して四方を囲い、庭の中には読書用の丸テーブルが一つに、私と兄様が腰かけているロッキングチェアーが二脚だけ。箱庭は面積にして五平方メートルもありませんから、テーブルと椅子を置いただけで一杯になってしまうのです。
狭いことを差し引いても、兄様の箱庭は私のお気に入り。居心地が良いだろう? と問われれば、天邪鬼な私でも首を縦に振るしかありません。それくらい兄様の箱庭は私にとって大切な宝物。いいえ、兄様と私がいて、箱庭は大切な宝物となるのです。
「もう大きくならないでね。箱庭に入りきれなくなってしまうから」
私の言葉に兄様はふふん、と意地悪く笑います。
「君には悪いけれど、もう五年もすれば僕は立派な紳士になっているだろう。背も伸びて声も低くなる。筋肉もついて、髭が伸びる。いずれ僕は父様のようになるんだ」
その言葉を聞いて、私はもう可笑しくって笑ってしまいました。
だって五年後の兄様は、父様のような巨漢の紳士にはならなかったのですもの。
五年後の兄様は母譲りの細身の青年へと成長しました。母親の性質を受け継いだものの、男子の宿命として声も低くなり、背も高くなり、体毛も濃くなった。父に似ようと母に似ようと、大人になった兄様は今の兄様とは似ても似つかない。私の忌み嫌う「男の人」に変貌を遂げてしまった。
だから、私は兄様を箱庭に閉じ込めたのです。
私とそっくりだった、あの頃のまま。
「イヤだわ、兄様。私はもう大きくならないでねと言ったのよ」
そのむかし、兄様が「男の人」ではなくまだ兄様だった頃のこと。
兄様は幼い私に箱庭を作ってくれました。薔薇の絵が印刷された包装紙を木箱に巻き、中にはドールハウス用の丸テーブルにロッキングチェアーを置いた、たったそれだけの小さな庭。来る日も来る日も私たちは箱庭で遊びました。お互いの名前がついた人形を手に、お茶会を開いたものです。
学校で親しい友達のできなかった私にとって、兄様だけが唯一の遊び相手。憎まれ口を叩くものの、飽きもせず私の人形遊びに付き合ってくれました。私は兄様が大好きでした。兄様と私は年も近く、外見も声も双子の如く似通っていました。兄様と一緒にいるとき、私はまるでもう一人の自分を見ているような気持ちになりました。もう一人の私は頭の回転が速く、口も達者で、友達もたくさんいて、まるで女の子のように可愛らしい男の子。兄様は私の憧れだったのです。
しかし、時が経つにつれ兄様の姿は私と異なってきました。
鳥の囀るようなソプラノは熊の唸り声のような低いものに変わりました。脂肪が落ちて体つきもがっしりとし、うぶ毛の色も濃くなりました。兄様の身長が伸びる度、私と兄様の心の距離もどんどん遠ざかっていく……現に、兄様は私と箱庭で遊ぶのを止めてしまいました。妹と遊ぶなんて格好悪い。人形遊びなんてやってられるか。そして、頻繁に男友達と戯れるようになりました。兄様の友達の中には父様と変わらないくらい立派な「男の人」もたくさんいました。
私は身震いしました。兄様が「男の人」になる。私にそっくりの、甲高い声を持つ男の子がいなくなる。私は一人ぼっちになってしまう。まごまごしていられない。兄様が大人になる前に、箱庭に閉じ込めてしまわなくちゃ。
ある晩、私は家族が寝静まったのを見計らってそろそろとベッドから抜け出しました。音もたてず兄様の部屋へ忍び込み、持っていた箱庭で兄様の頭を殴りつけました。鋼のように硬いマホガニー板で作られていた箱庭はこれしきの衝撃ではびくともせず、続けざまに五度、兄様の頭を殴りつけても亀裂一つ入りませんでした。兄様の真っ赤な血が、薔薇の包装紙を黒く染め上げる。それは兄様の身体から抜け出た魂。箱庭の中は兄様の血にたっぷりと満たされました。
兄様の成長を止めた一週間後、兄様はちゃんと私の元へ帰ってきました。私の部屋を忙しなく叩くものがあったので分かりました。兄様はいつも怒ったようにドアを叩くクセがあるのです。在りし日の兄様は相変わらず不機嫌な表情で、背は小さく、瞳は大きく、まるで女の子のよう。まるで私のよう……。
兄様は小鳥の囀りで私の名前を呼びました。それから私の手にしている箱庭を見て、
「やや、箱庭が真っ黒じゃないか。君は一体何をしたんだい。形も歪んでしまっているし、机も椅子もない。さては三階の窓から落としただろう? せっかく作ってあげたのに、しょうのない子だな」
兄様、と私は叫びました。兄様、兄様、兄様! 思わず首筋に縋りつくと、兄様は一瞬びくりと身を強張らせましたが、やがて私の頭を優しく撫でてくれました。兄様の身長は私と同じくらい。私はほんの少し背伸びをして、頬に頬を擦り寄せました。あの頃と少しも変わらない、私の大好きな兄様。
「君は赤ん坊みたいだなあ。箱庭の壊れたことがそんなに悲しかったのかい?」
「兄様、今度はもっと大きな箱庭を作って頂戴。私たちが入れるくらい、大きな箱庭。私たち、そこで毎日遊ぶのよ。いつまでもいつまでも、ずっと二人で遊ぶのよ。兄様、もう二度と大きくならないで!」
「〝ウンデナ〟の物語、読んだ?」
明後日の方向を向いていた兄様が、瞳だけを動かして私を見ます。
「〝ウンデナ〟? ……ああ、君のその本か。狂った人魚の話だろう?」
「ええ、そうよ。人魚・ウンデナは恋に破れて精神を病んでしまうの。海の底に洞穴を掘って、一生をそこで過ごすのよ」
ふぅん、と無関心に相槌を打つ兄様には構わず、私は「ウンデナ」の物語を読んで聞かせました。それはこんなお話です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
月夜の晩、人魚・ウンデナが岩礁に上りハープを弾いていますと、一隻の船が通りかかりました。船には隣国の王子様が乗っていました。王子様は言います。「なんと素晴らしい音色だろう! 僕はこんなに美しい音楽を聞いたことがない」。
それからというもの、王子様の船が通りかかる度ウンデナはハープを鳴らしてお迎えしました。やがてウンデナに王子様への恋心が芽生えます。嗚呼、あの方のお傍に行きたいわ。一言でいいから言葉を交してみたいわ。
ある晩、ウンデナは意を決して王室船に近づいていきました。「王子様、ハープを弾いていたのはわたくしです」。ウンデナは海面から顔を上げ、船から王子様が出てくるのを今か今かと待ちました。「やあ、君だったのか。何十年も僕に素晴らしい歌を聞かせてくれたのは」そう言って現れたのはしわがれた声と土気色の顔をした、余命幾ばくもないお爺さん。彼こそがウンデナの愛した王子様。ウンデナが初めて王子様にハープを聞かせた時から、なんと五十年もの歳月が経過していたのです。不老不死の力を持つ人魚は、人間が刹那に老いさらばえる生き物だということを知らなかったのです。気を病んでしまったウンデナは海の底深くに潜り、悠久の時を悲嘆にくれて過ごしました……。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本を読み終えると、兄様は手をひらひらと振りました。僕には理解不能、の合図です。
「ただの子供だましだよ」
それだけ呟くと、兄様は再びパイプを吸い始めました。